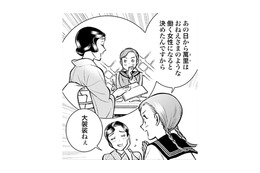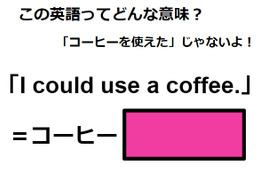この7月に新たに東京都議会議員に就任する高野たかひろさん。6月22日に投票が行われた東京都議会議員選挙に世田谷区選挙区から都民ファーストの会所属で立候補、定数8に対してみごと7位で当選しました。
25年2月末に退職するまで東京のキー局・TBSに勤務し、長くアナウンサーとして活躍しました。さわやかな笑顔のファンも多かったのではと思うのですが、なぜ政治、しかも都政を志したのでしょうか?
前編記事『年収ゼロどころか「このまま無職かもしれない」。東京都議当選、元TBSアナ高野たかひろさんが明かす「戦い抜く不安と恐怖」約3カ月の顛末』に続く後編です。
第一声は駅頭演説でスタート。「でも、マイクはどこで買うの?スピーカーは?」

こうして今からたったの4か月前、3月1日からスタートした政治活動ですが、「当初は何ひとつわからない状態だった」と振り返ります。
「まずは駅前に朝夕に立ち、通り過ぎる皆さまにご挨拶をして認知拡大につなげるという、基本の駅頭演説から始めました。ですが、立つにしても駅のどこに? そしてまず何をどう揃えるのか?」
スピーカーひとつ買うにもどこで何を? と手が動かなかったそうです。

「ポスターにもいろいろと決まりがあり、『選挙期間に入り、正式に候補者となるまでは、都知事と並んだ2連を使う』……『ん、2連??』。ある程度は自分でも調べないとわからないのです。あ、スピーカー?アマゾンでポチりました(笑)」
その反面、話すことにかけてはもう20年以上のベテランですから、最初の駅頭演説は「練習もせずに」立ったそうです。
「最初に立った日のこと、覚えてますよ。自己紹介、自分の背景と、作りたい社会について話しました。伝えたいことが固まっていて、これがやりたいから政治の世界に入らねばならない、お願いしますという内容が最初からありましたし、これは最後までぶれませんでした」
手応えは少しずつ増えていく。しかし「激戦区での新人候補」には安心がない

こうしてスタートした選挙活動では徐々に支援の輪が広がっていきました。
「最初は事情がわかっている人たちに、都議選に挑戦するのでお手伝いをいただけないかとお願いしました。パパ友、ママ友、娘と接点のあるご家族、そのお知り合い。支援学級のパパママや、幼稚園が一緒だったご家族……そのうち人が人を呼んで、ありがたいことに50名を越えるみなさんが集まってくださって」
雨の日も夜も毎日毎日、演説の際のチラシ配布やのぼりの設置などに交代で手を貸してくれたそう。ところで、いよいよ選挙戦に入ると、序盤から終盤に向かうにつれ、やはり「手応え」を感じるのですか? これまでそうした選挙を報道する側にいらしたわけですが。
「はい、やはりお声がけはコンスタントに増えていき、少しずつ『頑張ってください、応援しています』と言っていただけるようになりました」
それはもう、想像するだけで心が温かくなりますね!

「いっぽうで『政治は嫌いだ!うるさい!』と腹を立てている方にも接します。国政に対する文句をお話いただいたり……でも、こうした数多の声に耳を傾け続けると『この憤りにも何かのヒントがある、私たちは変えられる』と前向きに捉えられるようになるので不思議です」
えええ……そんな声に耐え抜いたとは、心が強いですね。強くないと政治はできないということでしょうか。
「いや、本当にあらゆる政治家の方々をリスペクトしました。この活動を皆さん朝晩続けてきたんだな、本当にすごいなと。これまで自分は耳を傾けることもなく前を通り過ぎていましたが、申し訳ないことをしていた。チラシ1枚でも受け取っておけばよかった、そこから学ぶものもきっとあったなと」
世間は言いたいことを言いますし、また政治家は悪口を言ってもいい対象と思われている節もありますよね。もともと人前に立つお仕事でしたからある程度は他人の言葉を浴びることに慣れていたのかもしれませんが、ご体験はお察しする部分もあります。
「そうして走り続けた選挙戦後半、期日前投票が始まると、こんどは『今日いれてきたわよ!あと少し頑張って!』という声が聞こえるようになりました。それこそ最初から遮二無二になって撒いてきた種が、ここにきて少しずつ芽を出してきたのかなと感じ始めました。しかし世田谷は激戦区、しかも都ファは現職と2人擁立ですから、確定的な安心というのはなく、ずっとずっと不安でした」
いよいよ迎えた投票日、出口調査の結果は「よい」ものの「安心はできないまま」で

こうして活動開始から約3カ月半、2週間の選挙活動期間も終えて、いよいよ迎えた投票日。高野さんは「疲労困憊でした」と振り返ります。
「土曜日の20時にマイクを収めて、投票当日は朝から選挙カーを神奈川まで返却に行きました。帰ってきてから投票所に向かいましたが、自分の名前を書くのにあれだけ緊張したことは人生で初めて、手がちょっと震えるくらいに」
その後は事務所で待機していたんですよね。候補者の皆さんは何か特別なルートで状況を教えてもらえたりするのでしょうか?
「まったく何もないですね、私たちもネットやNHKで知ります。いちど出口調査で6位、7位というのをネットで見ました。マスコミで報道していたときの立場ならば『普通はもう前後しないでしょう』と思う結果ですが、やはり当事者、しかも当落線上なので安心はできず、もう最後の最後までずっとハラハラと……」
ハラハラしたまま迎えた23時47分、党から電話が入り「選挙対策センターでは当確が張り出されました、おめでとう」。追いかけるようNHKで当確が出ました。もう午前0時前でした。

「大きな、本当に大きな安堵感に包まれました。ありがとうございました、自分のことなんですが、ここまで支えてくださったボランティアのみなさん、そして家族に対するありがとうございましたという言葉、もうそれしか出なかった。疲労困憊、そして、ありがとう……それ以外なかったですよ、本当に」
インクルーシブ教育には誤解も多い。これは「日本の未来を明るくする」手段のひとつ

こうして初挑戦でみごと都議に当選した高野さん。これから長い長い政治家としての道を歩き始めます。取り組みたいのはまず、インクルーシブ教育の推進です。
「障害とひとことでいっても千差万別です。我が家の娘は肢体不自由児で、移動には介助が必要ですが、知的面には問題がありません。ですが、支援学校で肢体不自由学級に通うとなると、学級には知的障害との重複障害の方もいらっしゃるため一緒に学ぶのは難しい。この解決策のひとつがインクルーシブ教育です」
可能性をもっと伸ばしてあげたいと考えても、現行制度はより手厚い支援が必要な子どもに合わせた設計であるため、通常級への通級を選んだ場合でも全カリキュラムの50%しか通えないのだそう。
「せっかく学ぶチャンスがあるのに制限するのは残念。でも、支援する人手が足りていないジレンマもよくわかります。ですから、人につく支援、インクルーシブ教育の選択制度が日本にも必要だと考えています。支援学校に行きたい子はそれを応援、学区内の通常学校に行きたい子は支援員をつけてしっかりサポートするインクルーシブの世の中。たとえばイタリアはそうなっています」

そもそもこのインクルーシブ教育とはスペシャルニーズのみではなく、社会全体をより心地よく安全な環境に整えていく一歩目でもあるといいます。
「日本社会では60%の方が障害者との接触を経験したことがないといいます。知見がない私たちはどうしても『面倒をみてあげている』と言う認識になります。でも、そうではない、学ぶことがいくらでもある。誰もが多様性を認めあい、ともに成長できる世の中を作る、それがインクルーシブ教育なのだということを、学校の先生も含めて認識してほしいですし、小さいときから『当たり前のようにいろいろな人がいる』状況を知ることがとても重要なのです」
高野さんのお嬢さんが通った幼稚園は、入園を志願した際にじゅうぶんに討議をかさねたうえで、はじめての車いす児童として迎え入れてくれたそうです。
「子どもは『なんで車いすなの』『なんで歩かないの』と普通に口にします。この、口にできる環境が極めて大事で、『この子にはこういう特性で』と当たり前に説明できることが大事。気を使って『そんなこと言っちゃダメ』と言い出さないために、まずは親の教育が必要なんです。娘の幼稚園は先回りせず、子どもたちがああしたいこうしたいと言い出すその話し合いに任せる方針でした。これができることが第一歩なのです」
同調圧力による均質化傾向が高いと言われることもある日本社会は、どうしても硬直しがちです。しかしこうして作り上げられていく社会は「許容ができる社会」になることでしょう。
「あらゆる困難を大変だね、応援していますと『他人ごと』にしてしまう社会ではなく、自分のこととして一緒に抱えていける、そんなインクルーシブ社会を作るために声をあげ続け、形を整えないとならない。それが私の目指す政治なのだと思っています」
高野たかひろ
1979年9月生まれ。宮城県石巻市、福島県いわき市で育ち、青山学院大学文学部フランス文学科を経てTBSに入社。 自然をこよなく愛し、アウトドアスポーツ、釣りやキャンプ、登山(特に北アルプス)はライフワークでもある。 家族は妻と9歳の娘、犬1匹。