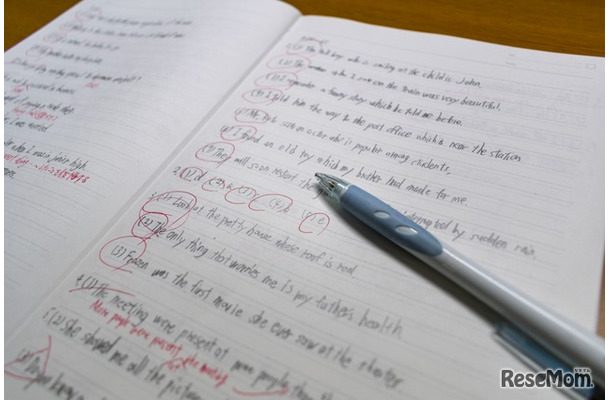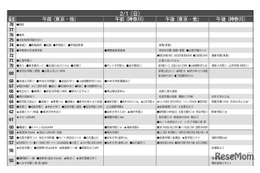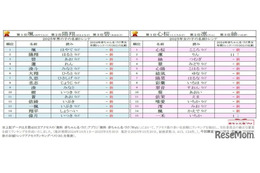しかし実際には、それは唯一の道ではない。今回の東京大学に在籍する学生100人へのアンケートで「中学受験をせず高校受験を経て入学した人の割合」は38%にのぼる。およそ4割が高校受験組という結果は、前述のような「中学受験をしないと東大には行けない」という固定観念とは少し異なる。
確かに、東大理科三類(医学部進学コース)に限れば、状況はやや異なる。過去10年間の理三合格者(約250名)を対象としたアンケートによると、高校受験組の割合は18.4%とかなり低い。つまり、理三レベルでは中学受験を経て一貫校に進んだ層が圧倒的多数である。
しかしながら、東大全体という広い母集団で見ると、必ずしも「高校受験=不利」とは言えない。むしろ、高校受験を経た学生の中には「中学受験をしなかったからこそ今の自分がある」と語る者も多い。
本稿では、実際の東大生たちの声やアンケート結果をもとに、高校受験のもつ教育的・心理的な意義を掘り下げてみたい。
「早期競争」からの自由…のびのびと学べる高校受験
中学受験は、言うまでもなく非常に早い段階から始まる。小学3年生の終わりには塾に通い始め、4年生で週3~4回の授業、5年生からは週6日ペースで勉強漬けという例もある。その中で、勉強を「自分の意志でやっている」と実感できる小学生は決して多くないのではないだろうか。
一方、高校受験は競争が始まる時期が数年遅く、精神年齢も高くなるために本人の主体性が発揮されやすい。東大経済学部3年のAさんはこう語る。
「自分は音楽が大好きで、小学校の間はピアノばかり弾いていた。親も無理に塾に行かせず、好きなことをやらせてくれた。そのおかげで集中力が鍛えられたと思う。中2から本格的に受験勉強を始めたけれど、短期間でも集中できて難関高校に合格できた」。
つまりAさんは「中学受験のレールに乗らなかったからこそ、自分のタイミングで伸びることができた」と考えているということだ。
また、中学受験では「小学校の段階で負けを経験してしまう」ケースも多い。努力しても合格できず、自尊心が傷つく経験をする子供もいる。高校受験の場合、そのような「早すぎる敗北感」を味わうことなく、精神的に成熟した時期に勝負できるという利点があると言える。「早くから競争に晒すことが成長につながる」との主張も一理あるが、子供の発達段階を考慮すれば、競争に挑むタイミングを中学生以降にずらすことには一定の合理性がある。
教科書の延長線上にある「王道」の試験
中学受験問題は独特だ。学習指導要領の範囲内からの出題とは言えど、つるかめ算や旅人算、立体切断問題など、学校の授業では扱わない特殊な題材が頻出する。ある意味で「中学受験専用」の知識を積み上げなければならない。それに対して高校受験の出題は、基本的に公立中学の教科書の範囲内だ。
理学部3年のBさんは帰国子女で、小学4年生まで海外で過ごした。帰国後に中学受験を検討したが、最終的に受験に至らなかったという。
「中学受験は特殊な訓練みたいに感じた。海外で学んでいた自分にとって、つるかめ算や集団塾のテキストの内容はまったく馴染みがなかった。でも高校受験は、教科書をきちんと理解していれば十分戦える内容だった。だから自分にも勝機があると思えた」。
確かに、高校受験は「基礎を固めた者が勝つ」試験である。裏を返せば、奇抜な問題に振り回されることが少なく、努力が成果に結びつきやすい。教育の本質が「基礎学力の積み上げ」にあるとすれば、高校受験はより教育的な形の試験であるとも言える。
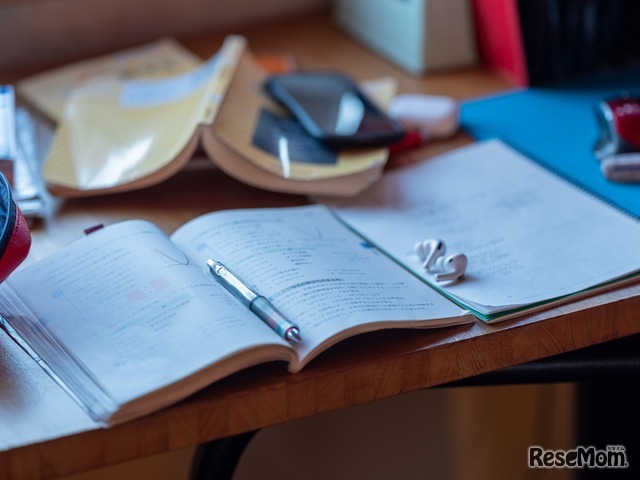 「自分の時間」をもてるという贅沢
「自分の時間」をもてるという贅沢中学受験をする小学生は、放課後も休日も塾や模試でスケジュールが埋まる。だが高校受験組の多くは、小学校時代に比較的自由な時間を過ごしている。
関西出身の東大経済学部3年Cさんはこう話す。
「小学校のとき、親から『〇〇中学を目指してみない?』と言われたけれど、通学に1時間もかかると聞いてやめた。その時間で本を読んでいたいと思った。結果的に地元の中学に進んで、高校受験では国語の成績がすごく良かった。小学生のころ本を読み込んでいたのが生きたと思う」。
Cさんのように、子供時代に「自由時間」を十分に確保できた経験は、後の学びに深い影響を与える。自由な時間の中で自分の興味を追求したり、内面的な集中力を培ったりすることは、単なる学力以上の価値をもつ。創造性や主体性といった力は、詰め込み学習の中では育ちにくい。
教育心理学でも、「自己決定感の高い学習ほど学習効果が長続きする」という知見がある。自ら選んで勉強する経験を中学期に得ることができる点で、高校受験ルートは心理的に健全だといえる。
「教えられないからこそ」身に付く自律性
中学受験を経て中高一貫校に進む生徒は、学校・塾・家庭の三位一体の管理システムの中で育つことが多い。与えられたカリキュラムをこなす訓練は徹底しており、学習面では効率的である。しかし、中には計画を自分で立てる経験や、失敗から立ち直る経験が少ないまま大学受験期を迎えるケースもある。
対して公立中→高校受験組は、ある程度の放任の中で自分なりの勉強法を模索することが多い。東大工学部のDさんは、「誰も勉強法を教えてくれなかったから、自分で試行錯誤した」と話す。
「朝起きたらその日にやることを付箋に書いて、全部終わらせるまで寝ないと決めていた。効率は悪かったけど、自分のやり方だから続けられた。高校でも大学でもこの方法でやっている」。
このように「自己流を確立する力」は、中学受験をしていない学生に、より特徴的だ。勉強の方法や時間配分を他人任せにせず、自分のリズムを作ることができる。これは大学以降の研究生活や社会に出てからも重要な資質である。
公立中学という「社会の縮図」
中学受験をして中高一貫校に進むと、学力層や家庭環境が似た生徒が集まりやすい。そのため、価値観の幅も狭くなりやすい。公立中学はその点、地域社会の縮図であり、学力も家庭環境も多様である。
教育学部のEさんはこう語る。
「公立中は、本当にいろいろな人がいた。勉強が得意な人も苦手な人もいて、価値観の衝突も多かった。でも、それが社会勉強になった。高校や大学に行っても、人間関係で動じなくなった」。
東大生の中には「中学受験をしていればもっと楽だったかもしれない」と語る人もいるが、逆に「公立中学で過ごした時間が人間的な成長につながった」と考える人も少なくない。多様な環境で揉まれる経験は、長期的に見て大きな財産である。
競争の始まりを遅らせるという選択
近年、発達心理学の研究では「早すぎる競争が学習意欲を削ぐ」ことが指摘されている。その観点からすると、高校受験ルートは、競争の開始時期を中学後半に遅らせることになる。
その結果、子供はそれまでの時間を自由に使い、興味関心を広げることができる。知的好奇心や内発的動機を育むために、周囲の人間は焦らず「待つ」ことも必要である。
また、模試や学校選択の中で「戦略的思考」を学び、自分の実力を見極め、現実的な目標を立てることは、社会に出てからの意思決定力にもつながる。
「高校受験組」の強さとは何か
中学受験は早期からの学習習慣を形成するという意味で確かに有効である。しかし、それがすべてではない。高校受験組には、以下のような強みがある。
精神的に成熟した時期に受験を迎えられる
教科書ベースの王道問題で、努力が成果に結びつきやすい
自由な時間の中で興味を深められる
自分で勉強法を確立する自律性が養われる
多様な人間関係を通して社会性が育つ
東大生の中でも、「中学受験をしなかったからこそ自分らしい学び方ができた」と語る人は少なくない。早い段階で塾に通い詰めるよりも、自分のペースで伸びる時期を待つこと。それもひとつの教育戦略であると言える。