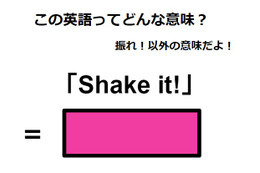こんにちは、40代男性ライターの鵜飼慎太郎です。共働きの妻・小学生の子ども1人の3人家族、普段は美術や書評を中心に活動していますが、ここでは個人的に気になる「お金の話」を取材しています。
前回のインタビューでは、女性IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活躍する千田愛さんに、「投資は怖い」という私自身の思い込みを打ち明けながら、50歳からでもまったく遅くない資産形成の在り方を伺いました。
「50代以降でも、運用しながら取り崩す方法を考えれば十分に間に合う」と、私のように40代半ばになってやっと老後資金を考え始めた人間にとって心強いアドバイスをいただいたのです。
しかし、「運用しながら取り崩す」とは具体的にどういうことなのでしょう? あと数年で50代に差し掛かかると、今度は生命保険の見直しや年金受給を控えての生活設計など、考えなければいけないことは山ほどあります。
今回はまさにそうした点を、より詳しく千田さんに伺いながら、少しずつ投資への向き合い方を学んでいきたいと思います!
【50歳からでも取り残されないお金の話】#3
資産運用とは決して「入金し続けないとならないもの」ではない。え、ごめんどういう意味?
老後資金の運用とは常に「時間をかけて増やしていく」イメージです。そもそも「取り崩し」だなんて、考えたことがなかった。改めて「運用しながら取り崩す」というのは、どのようなイメージを抱けば良いのでしょうか?
「まず、長期投資という言葉は投資を成功させる大原則の一つです。皆さんもお聞きになったことがあると思います。お客様の中には『一度投資を始めると投資をやめられない』、つまり投資を始めたら必要な時にお金を使えないと思われている方が多いなというのが実感です。 特に、保険を資産運用に活用されたことのある方に多い印象ですね。確かに保険は早期に解約すれば損をしますので、そのイメージが払しょくできないのかもしれません」
この「必要なときにお金を使えない」という不安と「運用しながら取り崩す」考え方は、具体的にどのように関係しているのでしょうか?
「投資はスタートしたらゴール(受取時期)まで『ほったらかし』で積み上げ続けるというのが、一般的な長期投資の考え方です。『運用しながら取り崩す』というのは、『必要なときには取り崩しながらも、残った資金をさらに運用する』というイメージです」
ごめんなさい、違いがよくわからない。貯金の引き落としのように、毎月5万円ずつ落としていくというようなことではなく?
「いや、その貯金の引き落としのイメージでいいと思います。引き落とした残りを運用し続ける。たとえば、長期投資のセオリーとしては、20年、30年のスパンで毎月定額増やしながらコツコツ運用するのが理想的だと言われますが、50歳以上の人がいきなり今から20~30年の資産運用と言われても、その期間にお金が自由に使えないなら『投資なんか無理!』となりますよね。だって、仮に60歳までに家の改築やら車の購入やらである程度のキャッシュが出ていくことが違いないですから」
みんな新NISAのオススメ信託の話だけしているけれど、「ゴールをどこにするか」こそ語られざる重要盲点で
いやー、投資って「何十年もただほったらかしにするもの」だと思い込んでたんですよ。でも、必要なときに少しずつ取り崩しながら運用し続ける方法があるなら、僕みたいに40代半ばとかアラフィフの人でも、まだまだ十分に間に合うということですよね。ところで千田さん、最近「資産運用はゴールを設定するのが大事」ってよく聞くんですが、具体的にはどういうことなんでしょう?
「鵜飼さん、それがとても重要なんです! 運用のゴール設定とは、『自分はいつ、どのくらいの資金が必要になるのか』を明確にすることです。たとえば、『60歳でまとまった資金が欲しい』『子どもが大学進学する時期にいくらか取り崩したい』など、将来のライフイベントを見据えた上でゴールの姿を考えます。特に50代から投資を始める場合は、残りの就労期間や年金受給年齢、退職金の見込み額なども絡んできますから、『何歳でどのくらい必要か』を明確にしておくことが重要なんです」
僕も「老後資金を増やしたい」っていう漠然としたイメージばっかり先行していて、どれくらい増やしたいのかとか、いつから取り崩しを始めるのかなんて、ちゃんと計画したことは一度もなかったんです。やっぱり具体的に考えないと、いつまで経ってもモヤモヤしたままになっちゃいそうだなぁ。
「そうなんです。それに、50代以降は生命保険の見直しやご両親の介護、場合によっては世界一周クルーズみたいに『定年後にやりたいこと』に合わせて大きなお金が動く可能性もあります。だからこそ、早めにゴールとなる時期や必要資金を把握して、『何歳でいくら手元に用意したいのか』から逆算して運用計画を立てることが大切になります」
たとえば、うちの場合は子どもがまだ小学生なので、大学進学なんかを考えるとどうしても大きな学費が必要になってきますよね。今すぐではないにしても、10年後とか15年後には必ず必要なタイミングが来るわけで……そこも含めてちゃんと考えないといけないのかと思うと、ちょっとドキドキします。
「そうですね。お子さんの教育資金を準備しつつ、自分たち夫婦のライフプランに合わせて『就労延長の可能性』『退職金』『年金受給のタイミング』『iDeCo』などを総合的に考える必要があります。いざというとき、年金を繰り下げれば受給額を増やすことも可能ですし、就労を延長すれば給与収入を確保しながら運用資金を取り崩すペースを抑えられますよね」
なるほど…。そうなると、投資で増やすだけじゃなくて、いつまで働くかとか、年金をいつから受け取るか、保険をどうするか――そういった生活設計全体を見据える必要がありますね。うーん、やることが多くてちょっと頭がパンクしそうです(笑)。
「確かに、一度に考えることが多いとそう感じますよね。でも、実は生活設計の中で、意外と見逃されがちなものがあるんですよ」
え、何ですか?
「公的年金なんてあてにならないから、入っても意味ないよ」と言う人がいますが、それは論外
「鵜飼さん、公的年金が終身保険のような特徴を持っていることをご存じでしたか?」
終身保険って、民間の保険商品だけかと思ってましたけど、公的年金もそういう考え方ができるんですか?
「実はそうなんです。公的年金は終身で受け取れる仕組みなので、長生きすればするほどその恩恵が大きくなる特徴を持っています。だからこそ、年金を繰り下げて受け取れば毎月の受給額を増やすこともできるんですよ。これによって、いざというときの取り崩し資金を抑えて“資産寿命”を延ばすことが期待できます」
なるほど、公的年金は一生涯もらえるものだから、死ぬまで保障される“終身保険”みたいなものだと考えられるわけですね。そう考えると、年金を繰り下げるかどうかって、もっと慎重に考えなきゃいけない気がしてきました……!
「年金を繰り下げるかどうかは、就労延長や健康状態、家族構成などによっても判断が変わります。どうしても早めにお金が必要なケースもありますし、逆に、働き続けられそうなら年金を後ろ倒しにして、より多い受給額を狙うのも手ですよね。いずれにしても、公的年金は“終身”という大きなアドバンテージがあるので、いざというときの安心感は大きいんです」
そう聞くと、本当に公的年金の大切さがよく分かります。投資のことばかり考えていましたが、改めて年金の存在って大きいですね。
「そうなんです!だからこそ、IFAとしては『資産運用』だけを見るのではなく、鵜飼さんのライフステージや価値観、家族構成などを踏まえて、最適なゴール設定をお手伝いするのが役割だと思っています。ゴールが定まっていれば、どんな運用商品を選ぶべきか、いつごろ取り崩しをするか、といった具体的な戦略を立てやすくなりますから」
確かに…家族や仕事の事情も含めて資産形成や運用を考えていかないといけないってことですね。
今回は「運用しながら取り崩す」考え方について伺いました。次回は「運用に基づいて保険を見直し、お金の置きどころを整理する」ことについて伺います。
つづき>>>そもそも新NISAってオルカンでもSP500でも「何歳まで積み立て続けるのですか?」その答えは
お話/千田愛さん
IFA・ファイナンシャルプランナー。製薬会社MR、広告会社営業を経て投資運用会社で運用の基礎を学ぶ。育児による専業主婦時代を経てふたたび金融の世界に戻り、FPとして主に女性のライフプラン設計に寄り添う。IFAの資格取得後は人生トータルでのお金の使い方を主眼に、貯めるだけでなく「お金をよりよく使って生きていく」人生設計に寄り添う。
(取材・文/ライター・鵜飼慎太郎)