
こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。
私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。
1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。
【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】
「白露」のころ。今年はまだまだ露がおりる気温にはなりませんが

暦の上ではすっかり秋なのですが、「最近は夏が長くなり、秋が短くなった」とよく言われるように、日中の暑さはまだ残っていますね。スーパーの青果コーナーで、ぶどう、梨、柿、栗を見かけると「暑さは残っていますが秋は確実に訪れているんだな」と感じたりします。
今年、25年の白露は9月7日から22日まで。昼夜の気温差が大きくなって、朝に露がおりるころです。草におりた露は透明ですが、光が当たって「白」と表現するところは風情ですね。空気が冷え始めるということは、いよいよ残暑の終わりも近づいてきたということ。朝露が日の光をあびて白く輝く季節。ようやく秋を肌・身体で感じられる気候になります。
熊本には天草(あまくさ)という海が近くにあります。夏の間は暑さもあるので夜釣りでのイカ釣りに徹しますが、肌に接する空気から秋を感じられるようになると、いよいよ昼釣りの時期になります。熊本から少し外海に出た東シナ海で釣りをするとカンパチの幼魚(熊本ではネリゴと呼んでいます)が釣れるようになります。
秋の入り口になにより気遣いたいのは「肺」の機能です

秋に活躍したい「肺」。その機能はいくつかありますが、まず1つ目として挙がるのが呼吸の担当。西洋医学での認識と少し異なるのですが、中医学での呼吸は「肺」と「腎」の共同作業とイメージしています。もう1つ、肺がつかさどる重要な役割として「宣発(せんぱつ)」と「粛降(しゅくこう)」があります。宣発は身体の上や外に向いた作用、粛降は身体の下に向けて散布する作用です。
身体の機能の中心となる五臓について、中医学は中国の王朝に見立てたストーリーで表現することがあります。「心の機能」は君主(≒王様)、「肺の機能」は臓腑の中で一番上に位置しているので、君主の頭の上に掲げる傘とイメージします。この傘は気・津液(しんえき)、栄養、つまりエネルギーを身体中にいきわたらせる役割を持っています。いちど気を上げるのが宣発、上げるだけだとなくなるので下げるのが粛降です。
“肺の機能にうれしい食材”でおススメなのは、らっきょう、シソ、山芋、しめじ、牛乳、パセリなどが挙がります。
ちょっと違った味わいを楽しめる!「らっきょうとシソの混ぜごはん」

これらの“肺の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「らっきょうとシソの混ぜごはん」です。“らっきょう”というとカレーライスの時に…が定番ですが、ちょっと違った使い方をして肺の機能に嬉しいレシピにしてみました。
作り方はかなりシンプルです。らっきょうは薄切りにします。シソは2~3mm幅の細切りにして、塩もみをした後、水洗いして絞っておきます。これらを炊いたごはんに混ぜて、白ごまをふりかけたら出来上がりです。
シソは「体表の毛穴を開いて肺の機能を助ける」働きが期待できます。ここに「身体の乾燥に潤いを補う」働きが期待できるらっきょうを合せるだけなのですが、シソの香りとらっきょうの甘酸っぱさで驚くほどに食が進むレシピになりました。白ごまはお好みでふりかけていただければと思いますが、白ごまには「肺と関係する大腸に潤いを補う」という働きかけも期待できます。見た目・味・香りに加えて、効能面からも“ひとふり”いただくだけで身体が喜ぶのではないかなと思い、おススメさせていただきました。
山芋ステーキのしめじミルク煮。ベビー帆立もプラスして完璧!

2つ目も肺の機能を補うレシピとして「山芋ステーキのしめじミルク煮」を紹介します。肺の働きで「身体の上や外に向いた作用」の宣発(せんぱつ)を助けるしめじと、「身体の下に向けて散布する作用」の粛降(しゅくこう)を助けるパセリを合せてレシピしてみました。
作り方は、こちらも意外とシンプルです。山芋(200g)は皮をむいて約1cm幅の輪切りにします。しめじ(1/4株)は石づきを取って、1本ずつに分けます。ベビー帆立(10個)はみじん切りにして、水(100ml)・酒(大さじ1)・鶏ガラ粉末(小さじ1/2)・胡椒(少々)と合せます。小さな器に片栗粉(大さじ1)と牛乳(大さじ2)を入れて混ぜ合わせます。
フライパンにごま油をひき、山芋の表面に焦げ目がつくように、塩をふりながら4~5分焼きます。裏面も同様に焼いて焦げ目がついたらしめじを加え、ベビー帆立と合せた調味料を加えてフタをして2~3分煮ます。ここに牛乳(170ml)を入れて、沸騰したら牛乳に溶いた片栗粉を加えてとろみをつけます。器に盛りつけて、上からパセリを加えてたら出来上がりです。
先ほど紹介したように、しめじは「身体の上や外に向いた作用を助ける」働きが期待でき、パセリは「身体の下に向けて散布する作用を助ける」働きが期待できます。
この2つの特長を生かすことを目的として、「身体に元気の素を補って、肺の機能を助ける」働きが期待できる山芋を焦げ目がつくように焼くことで美味しさを引き出し、「身体に潤いを補って、肺の機能を助ける」働きが期待できる牛乳で煮るミルク煮にしてみました。
少し風味をつけるために加えたベビー帆立も「身体に潤いを補う」働きが期待できるので、味・香り・効能面からも身体が喜ぶと思い、加えて完成したレシピです。
熊本で高菜が食べられる理由も、驚くほど理にかなっているのです

九州に来て25年程経ちますが、よく目にするようになったのが「高菜」です。高菜は小松菜などが属するアブラナ科の葉野菜で、主な産地は九州。高菜漬けは加工食品として道の駅などで販売されたり、とんこつラーメンのトッピング具材として使われていたり…と常備菜としてよく目にします。その作用を調べてみると「宣発」に働きかける作用がありました。食材の作用を知って「この時期の肺の機能を助けてくれる大切な野菜」と認識すると、今年も大きく育っているだろう高菜畑を目にしたくなりました。
道の駅などで売られている高菜漬けには、白ごまとウコンを加えてごま油で炒めた、少しピリリと辛い味のものもあります。白ごまは大腸の働きをサポートしてくれますし、唐辛子は毛穴の開きをサポートするので肺の働きを助けることにつながります。
黄色く見える高菜漬けはウコンの色が多いのですが、ウコンは肝の気のめぐりに働きかけてくれます。ストレスがたまってしまった時に出るストレス咳にまで作用が期待できる…と思うと、高菜漬けがとても養生食に感じられます。
熊本城主が加藤清正だったころから、熊本の地は養生、自然と身体のバランスを意識していたように感じます。熊本城の本丸には大きな銀杏の木が植えてありますが、あれも籠城に備えてのことだと言われています。私たちの再春館の名も、肥後藩主が細川重堅公の時代に創設された日本初の公立医学校で、医学を学びたい人に門戸を開いた藩校「再春館」に由来しています。自然とともに生きる土地に、私は呼ばれていま仕事をしているのかもしれません。
じわじわと人気…「田野岡メソッド」は書籍でもご覧いただけます!
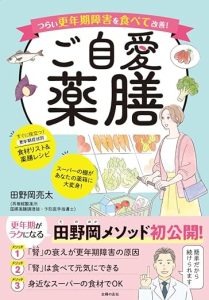
「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?
日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。
田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!











