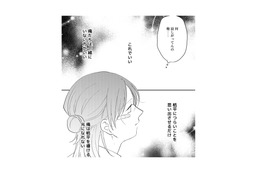こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。
私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。
1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。
【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】
今年はずっと暑いままですが、本来は「暑さが少しやわらぐころ」

今年の「処暑」の暦は8月23日~9月6日。「処」とは、止まる・留まるという意味。8月後半になると、朝夕は暑さがおさまり過ごしやすくなります。涼しさを含む風が吹き始めて、夜に虫の音が聞こえ始めるころです。という暦なのですが、今年はずっと暑さが続きましたね……。
上の画像は熊本県の阿蘇の稲穂です。阿蘇山はカルデラ地形なので、阿蘇地域に入ると周りを外輪山にぐるっと囲まれた平地になりますが、太陽が近く、まわりを山の緑に包まれているからか、どこか神々しさを感じたりします。
また、阿蘇山は雨が浸透しやすく、地下水となって蓄えられた後「湧水」となって湧き出す特長があります。阿蘇で育った新米を見ると、暑い夏でしたが「自然は暦通りに営まれているのだな」と実感します。夏場の太陽の光をいっしんに集めた作物たちが、お米だけでなくいま実りのときを迎えています。
「処暑」まだまだ暑い8月末から、少しずつ空気が乾いてくる9月上旬

暑さと湿度を感じる空気に包まれる8月までは、暑さで頑張る「心」と湿度を嫌う「脾」の機能をお話のメインキャラクターとさせていただきましたが、これからの秋は「肺」の機能が主役となる季節になります。「肺」の機能は、呼吸を担当して、身体全体の気のコントロールをしています。全身に気をいきわたらせるので、「気」にとって肺の機能はとても大切な存在です。
肺は潤っていると心地が良く、温暖を好む性質があります。8月下旬はまだ湿度も暑さも残っていたので、潤い・温暖を好む肺の機能にとっては心地が良く、元気に呼吸・気のコントロールをしたくなる状況でした。最近の日中の暑さは程度が桁外れですが、夏場の朝晩に身体が動きやすく感じるのは、呼吸と「気」の動かし方がうまく出来ているからかもしれません。
これから秋が深まると、人間が包まれている空気の「乾燥」「寒さ」が少しずつ増します。肺の機能にとって心地よい「潤い」「温暖」とは真逆のことなので、肺にとっては環境が一気に逆転して嫌なことが忍びよる季節となります。これからの季節は「肺の機能」を意識してケアしてあげることが大切になります。これからの時季のメインキャラクター「肺の機能」にとって、環境が一気に真逆に変わる季節だからです。
肺を元気にしてあげる食事を心がけてください。きのこが旬であるには意味がある

“肺の機能にうれしい食材”でおススメなのは、えりんぎ、しめじ、いちじく、バター、かぼちゃ、クコなどが挙がります。
これらの“脾の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「キノコといちじくのバターしょうゆ炒め」です。お盆を過ぎてからスーパーで目にすることが増えてきた“いちじく”。秋に旬を迎えるキノコと合せてレシピにしてみました。
作り方は、まず“いちじくの下味づけ”をします。いちじくの皮をむいて4等分し、それをさらに2~3等分します。ボウルに入れて、すりおろし生姜(1/2片分)・酒(大さじ1)・しょうゆ(大さじ1/2)と合せて10分ほど置きます。
次に“キノコのバターしょうゆ炒め”を作ります。えりんぎは5mm厚の短冊切り、しめじは石づきを外して1本ずつに分けます。フライパンにえりんぎ・しめじを入れて、バター(20g)・しょうゆ(大さじ1)・塩(小さじ1/2)を加えて、キノコがしんなりするまで炒めます。
キノコがしんなりしたら、下味をつけたいちじくを合せて、一煮立ちさせます。器に盛りつけて、上から刻んだ小ねぎをかけたら出来上がりです。いちじくのほのかな甘さをすりおろし生姜の辛みで引き立ててみました。
秋の味覚“キノコ”の季節が始まりました。えりんぎは「身体に必要な気と、身体に潤いを補う」働きが期待でき、しめじは「気と血を補って、肺の働きを助ける」働きかけが期待できます。キノコの香りと旨味を引き出すバターには「身体に潤いを補って、乾燥を潤わせる」働きかけが期待できます。
「脂質は太る」と油脂は敬遠されがちですが、湿潤の夏から乾燥の秋に季節が移るこのひと時だけ、身体の状態維持のためにバターの効能をお借りしても良いかな…と思っての提案レシピでした。ほのかな甘みのいちじくは「身体の潤いを補い、咳を鎮める」働きかけが期待できます。いちじくの甘みがキノコの風味に隠れてしまわないように、すりおろし生姜と合せてみました。生姜の辛みの感じ方は人それぞれですので、すりおろし生姜の量は調整いただけると良いと思います。
つづき>>>もうひとつ、かぼちゃのレシピもご紹介しましょう