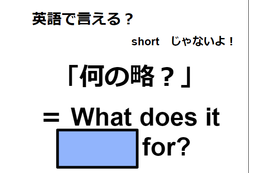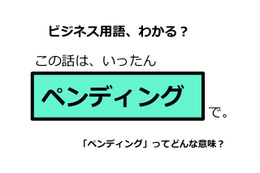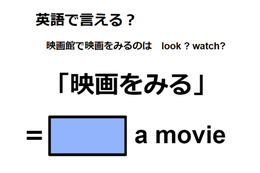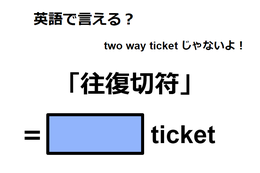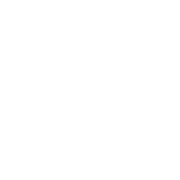様々な価値観が多様化する昨今、「家族像」もそれぞれに唯一の在り方が描かれるようになりつつあります。
この「家族のカタチ」は、私たちの周りにある一番小さな社会「家族」を見つめ直すインタビューシリーズです。それぞれの家族の幸せの形やハードル、紡いできたストーリーを見つめることは、あなた自身の生き方や家族像の再発見にもつながることでしょう。
今回ご紹介するのは、石川県能登町に暮らす中野千絵さんです。
2024年1月1日の能登半島地震の当時、千絵さんの長女は小5、長男は小2、次女は3歳。突然の親類との共同生活に、不安に襲われた子どものケア。さらには、夫が店主を務める洋菓子店の再開準備まで……。目まぐるしい変化の中に身を置きました。
未曾有の事態に荒々しく放り込まれたとき、家族のカタチはどう変化するのか? 震災から10カ月を迎える今、千絵さんにお話を聞きました。
【家族のカタチ #2(前編)|能登編】
能登の海辺の洋菓子店と、その家族を襲った大地震

カフェで接客する千絵さん。客席の眼前には恋路海岸が広がる。
石川県・能登半島の東岸。能登町におよそ1kmにわたって広がる恋路海岸は、能登半島の国定公園であり観光名所の一つです。浜に打ち寄せる波は穏やかで、水平線から朝日が登る時間帯には空と海は紺碧から紫、そしてオレンジへと、刻一刻と色合いを変えながら見事なグラデーションに彩られます。そんな美しい海が窓いっぱいに広がるのが、「なかの洋菓子店」。千絵さんの夫・洋人(ひろと)さんが店主を務めるお店です。
「2005年に東京や金沢で修行を積んだ夫が店をオープンしてから、たくさんの常連さまが通い続けてくれていて、感謝しかありません」と話す千絵さん。

ショーケースにならぶケーキは、能登のフルーツの旬に合わ
せて変わっていく。それが常連客の楽しみのひとつだそう。
能登ならではの新鮮なフルーツやこだわりの食材を使い、「わざわざ足を運んでくれるお客さまにいかに喜んでもらうか」を考え抜いたアイデアが加わり生まれるケーキたち。多くのリピーターのお客さま以外にも、最近はインスタグラムなどでお店を知って遠方から買いにきてくれる方も少なくないのだとか。
そんなお店を見守りながら、13年前に結婚して以来、育児中心の日々を送っていた千絵さん。ところが昨年9月、ケーキ店併設のカフェスペースのオープンが決まると、本格的にカフェの中心スタッフとしてお店に関わるようになりました。
「私がお客さまと接するのは、コーヒーやケーキをお出しするほんの一瞬ですが、そこで伝わる思いもあると思うんです。お客さまに心からくつろいでもらえるように、こちら側がどんなに慌ただしくても、必ず一呼吸。ゆったりした気持ちと動きで接客することを心がけています」と穏やかにほほ笑む表情に、その人柄が滲み出ます。
こうして店の新たなステージを切った、わずか3カ月後。千絵さん家族を襲ったのが、あの震災でした。

朝日がのぼる時間帯の恋路海岸。
車の中はすし詰め状態。暗闇に包まれ過ごした震災当日の夜
千絵さん一家は、夫婦と3人の子ども、洋人さんの母親の6人暮らし。歩いて数分の場所には、千絵さんの両親が暮らす実家があります。
「あの日は、夫と長女・長男は近くの私の実家に遊びに出かけて、風邪気味だった次女は私とお留守番。夕方近くになって、『ちょっと酔っぱらったから』と夫だけ私の実家から一足早く家に帰ってきました」。
当たり前のいつも通りのお正月。ところが、夫の帰宅から1時間ほど経った頃、のんびりゴロゴロしながらテレビを見ていた千絵さんたちを大きな揺れが襲ったといいます。
「その瞬間、実家にいる2人の子どものことが頭をよぎりましたが、まずは自分の身を守るので精一杯でした。夫は次女を迷わず抱え、寝転んでいた義母が立ち上がるのも待たず引きずって。『とにかく出よう、家の外に出よう』と、とにかく必死でしたね」。
揺れが落ち着いて間もなく、千絵さんの両親に連れられた我が子2人が帰宅し、ようやくお互いの無事を確認することができたのだそう。でも、その余韻に浸る時間などありません。お正月で帰省していた他の親族たちとともに、取るものも取り敢えず3台の車で避難所に向かったといいます。
「まずは向かったのは、家から一番近い小学校。そこまでの上り坂がめちゃめちゃに割れていました。それまでとはまったく別の風景でしたね。いざ到着した小学校は、被害が大きく立ち入り禁止。そのあと向かった中学校も、断水と停電。トイレも使える状態ではありませんでした」。
結局、近所の知り合いの家の駐車場に停めさせてもらい、車中で一晩を過ごしたのだそう。3台の車にそれぞれ4~5人が乗っていたといいますから、とても体が休まる状態ではありません。
「子どもたちはわけのわからない一日に疲れ果ててぐっすり眠っていましたが、車中はとにかく狭いんです。快適に過ごそうとしても、何も持たずに飛び出したから工夫のしようがない。そんなわけで23時ごろ、私と夫で荷物を取りに自宅に歩いて戻りました。停電で真っ暗でしたから、スマホの明かりをぽつんとつけて。その小さな明かりだけが頼りでした。
家に到着後はそのまま土足で上がり込んで、子どもの薬に靴に、毛布……手当たり次第にかき集めましたね。家に1台残っていた義母の車がパンパンになるまで荷物を詰め込み、家族のもとに戻りました」。
そうしてなんとか迎えた翌朝。昨夜夫婦で歩いた5分の道のりを改めて眺めてみると、地表から1メートルも飛び出したマンホールや、砕けた道路があちらこちらに。一度は頼った小学校は、玄関から崩れていたといいます。
「あの時は真っ暗だったから何もわからず歩けましたが、朝になってその風景を眺めたとき初めて、想像以上の景色の変わりように怖くなりました。『こんなに被害が大きい場所を通っていたんだ』って」と千絵さんは当時を振り返ります。
14人で3週間。ガレージでの避難暮らしを乗り越えるために大切だったこと

震災直後に生活拠点としたガレージ内でいとこ(左端)と過ごす千絵さんの子どもたち。
震災翌日、自宅に戻った千絵さんたちは、自宅の状況を改めて確認。すると、庭の大型ガレージに大きな被害がなかったことがわかりました。そこで、しばらくはこのガレージを生活拠点にすることを決意。家族・親族総勢14名で過ごす日々が始まったといいます。
「まずは自宅の2階にある寝室からベッドのマットレスを放り投げて降ろしたり、防災対策として買っておいたエアマットを膨らませたりして、寝床を整えました。
子どもたちは地震で味わった不安がありつつも、非日常の生活に小さな楽しみを見出しながら過ごしてくれました。こんな状況下でも希望を忘れない子どもの笑顔に、大人たちは救われましたね」と話す千絵さん。
とはいえ、被災直後の心理状態の中、普段は生活を密にしているわけではない身内と狭い空間で同居生活することにお互いストレスが生じるのは当然のこと。

断水が続き、多くのバケツで雨水を溜める工夫も。
「私たち家族と義母、私の両親、90歳を越えた義母の叔母……さらにあと2家族ほど。それだけ大人が集まれば、多少は思いがぶつかるのは当たり前ですよね。それに加えて、震災後はみんな頭も心もゴチャゴチャです。全体をまとめようと頑張ってくれていた夫も、疲れが溜まると余裕がない反応になる瞬間もありました。
――多分、地震の直後は、みんな生き抜くことで頭がいっぱいなんです。食べて、トイレに行って、雨が降れば生活用水として確保して。とにかく必死なんですよね。ところが4~5日経つ頃には少しずつ周りが見えてきて、疲れが出てくる。他人の言動に敏感になったりするのも、ちょっと状況が落ち着いてきてからだったと思います」。
非常時の家族に大切だったのは、役割・距離感・いつもと変わらぬルーティーン

状況や人数の変化に合わせて家電や家具などを追加するなど、ガレージ内の暮らしを快適にするための工夫を重ね続けた
衝突や葛藤がありながらも、互いになかなか逃げ場のない状況下で、この時期ならではの家族のカタチを、千絵さんたちはどのように維持していったのでしょうか。
「一人ひとりがそれぞれの役割を果たすことがとても大切だと感じました。たとえば、料理が得意な人は料理を作る、話を聞くのが苦にならない人は聞き役に回る、という風に」。
誰かの言いなりになったり、非常時だからと我慢し合うのではなく、それぞれが無理なく発揮できる得意を持ち寄ってデコボコを補い合うことが関係を円滑にしてくれた、と振り返る千絵さん。
それに加えて、互いの物理的な距離を確保することも有効だったとか。
「ガレージ暮らしが始まって1週間ほど経つと、それぞれの家族が別の親族の家に泊まりに行くという工夫も始まりました。弟が暮らす金沢に私の両親が出かけたり、金沢のすぐ北にある内灘町の親族の家に私と子どもで泊まりに行ったり。
数日たてば拠点のガレージには戻るのですが、それでも違う場所や人と接すること、物理的に人との距離を取れることが大きなリフレッシュになりました。
あとは、寝るときだけは家の中で、ということも徐々に増えていきましたね。昼間にみんなで協力しながら荒れた家の中をせっせと片付けて、高齢者や疲れが溜まった人は家の中で休める環境を整えました」。
一方で、非常事態に身を置き続ける子どもたちへの心配も尽きません。千絵さんが大切にしたのはクールダウンのための日常でした。
「子どもたちは、この状況下の生活を前向きに捉えていましたが、それはつまりずっと興奮状態にあるということ。だからこそ、クールダウンできる“普通”をいかに作り出すかを意識しました。
お絵描き、雪遊び、家族みんなで楽しむカードゲーム……。食べて、寝て、話をして、いつも通りの方法で遊ぶ。生活環境こそ非日常でしたが、そんな時こそいつも通りのルーティーンをできるだけ再現するよう心がけました」。
こうしてガレージの屋根の下、家族関係と環境のチューニングを繰り返した千絵さんたち。日常を取り戻す準備を整え、徐々にそれぞれの家庭へと戻っていったのだそう。14人全員がガレージ暮らしを終えたのは、あの地震から、およそ3週間が経つ頃でした。
▶つづきの【後編】では、震災後に育んだ「新たな親子関係」について、お話をお伺いしました。__▶▶▶▶▶