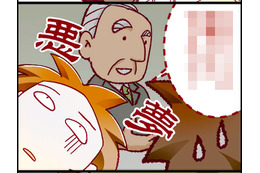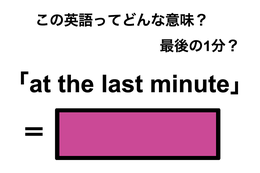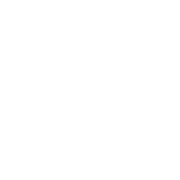日本人の閉経は平均して52歳前後。閉経の前後5年を更年期と呼ぶので、47歳から57歳がこの時期に当たる人も多いでしょう。フェムテック元年の2020年以降、日本でも更年期を取り巻く環境もやや改善傾向にあるとは感じますが、それでもまだ情報はなかなか取りにくく、他者もサポートしにくいのが現状です。
「これまで、更年期障害は産婦人科医師が一手にその診断と治療を担ってきた分野です。が、私は従来考えられていたよりももう少し『生活習慣の影響を受ける』ような側面があるのではと考えています」
こう語るのは、オトナサローネではおなじみ、川崎医科大学総合医療センター産婦人科特任部長 太田博明先生。1990年代から現在まで一貫して日本の更年期医療、女性医学の先端に立ち続けてきた太田先生に「日本人女性の更年期、その特徴と解決に向けて」というテーマで5回に分けてお話を伺います。(1/2/3/4/5この記事は5回中の2回目)
5大更年期症状「のぼせ」「ほてり」「発汗」「抑うつ」「不眠」のうち「いちばん防ぎたいもの」は?
私は慶應時代に「慶應式中高年健康維持外来調査表」を作成しました。更年期のいわゆる「5大症状」や、それ以降の中高年の健康維持に着目した40項目のアンケートです。その後の実証で更年期のみならずそれ以降の健康の維持・増進を把握するのに適していると裏付けされ、現在に至るまで活用されています。
というのも、1991年の時点では、外国人を対象として作成された「クッパーマン更年期障害指数」」が我が国では専ら使われていました。更年期障害には人種差があることから、日本人に適合した更年期指標で更年期障害を評価すべきであることを日本産科婦人科学会生殖・内分泌委員会で提案、自ら小委員長となり、2001年に21項目からなる学会認定の「更年期症状評価表」を作成しました。「クッパーマン更年期障害指数」「簡易更年期スコア(SMI)」は更年期症状を点数化するものですが、私は点数化には意義を感じず、症状強度の把握を行う指数が必要だと感じていたからです。結果的に単一の症状であっても強度(+)が高ければでQOLを損なうことが認められ、その精度が評価されました。今日においても「更年期症状評価表」は存続しており、診療で使用されています。
その調査での有症率からいうと、更年期症状の5大有症率は、「のぼせ」82.9%、「ほてり」81.6%、「発汗」77.6%、「抑うつ」55.3%、そして「不眠」53.8%などの順でした。これはおよそ今日でも同様です。
このころホットフラッシュ制御として「1日に10回以上のひどいホットフラッシュがある人はエストロゲン欠乏だけではなく、他にも要因があるのではないか」と考え、調査に乗り出しました。すると、アミノ酸のβ-アラニンの増加が見られました。現在ではプロテインとして市販されている成分ですが、大量に投与するとホットフラッシュが出ることがあります。本件はホットフラッシュ抑制の研究としては成就しませんでしたが、ホットフラッシュにはエストロゲン以外にも何らかのこうした関与因子があると考えています。
「抑うつ」こそが更年期障害最大の「難所」。つづいて「不眠」も手ごわい
さて、これら5大症状のうち、何がQOL(生活の質)に一番関係するかというと、「抑うつ」が断然強いのです。のぼせ、ほてり、発汗も大変でしょうが、抑うつはQOLに非常に大きな影響を及ぼします。その次が不眠でした。
人口ピラミッドでいうと、1991年に私が中高年健康維持外来を設立した時期は、団塊の世代(1947~49年生まれ)の人々は更年期が始まる45歳のちょっと前でしたが、その翌年1992年、最大人口を占める団塊の世代の更年期が始まるということで、一気に10大学くらいに更年期外来ができ、更年期外来のブームが到来しました。
そして2025年現在、今度は最大人口のトップとなった団塊ジュニア(1971年~74年生まれ)が更年期にさしかかっています。この世代は分娩が非常に多かったので、私たち1970年卒の新米の産婦人科医は一晩に10人、20人と生まれる赤ちゃんたちに一睡もできなかった経験があります。この層が今や最大人口となり、やがて高齢化していくわけです。更年期医療は、団塊世代が更年期を迎えた1990年代に1回目の最盛期を迎えました。そして団塊ジュニア世代が更年期を迎える2020年代半ばからは2回目の脚光を浴びると予測しています。
性別で比較しても、日本人は筋骨格系の症状、つまり「肩こり」「関節痛」などが多い傾向があります。体格が華奢(きゃしゃ)にできていることも関係しているかもしれません。女性は男性の2倍以上、肩こりを訴えますし、関節痛や腰痛にも性差が見られます。
その他、ホルモンに由来しないものも含めて、更年期女性が訴える症状の首位は「肩こり」「腰痛」「手指の関節痛」「体がだるい」「頭痛」。興味深いことに、これらは厚労省の国民生活基礎調査で0歳から全世代の日本人が訴える自覚症状の5大主訴と共通しています。つまり、若い頃から痛かったり、不具合があったところが、更年期からそれ以降一生に渡る痛みや不具合として噴出してくるのですね。
つづき>>>更年期症状は刻々と移り変わっていく。しかし「治療」にたどりつく人は今でも10%程度、我慢してほしくないのに
お話/婦人科医・医学博士 太田博明先生
1970年慶應義塾大学医学部卒業。80年米国ラ・ホーヤ癌研究所訪問研究員、91年慶應義塾大学産婦人科講師、95年同大学産婦人科助教授、2000年東京女子医科大学産婦人科および母子総合医療センター主任教授。その後国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授、山王メディカルセンター・女性医療センター長就任し、19年より3年間藤田医科大学病院国際医療センター客員病院教授を兼務、21年より現職の川崎医科大学産婦人科学特任教授、川崎医科大学総合医療センター産婦人科特任部長を務める。日本骨粗鬆症学会元理事長、日本骨代謝学会および日本女性医学学会元理事・監事を務め、日本抗加齢医学会では元理事、前監事を務める。国内の女性医学のパイオニアとして今なお第一線での研究と啓蒙を続ける。1996年日本更年期医学会(現日本女性医学学会)第1回学会賞受賞、2015年日本骨粗鬆症学会学会賞受賞(産婦人科医で初受賞)、2020年日本骨代謝学会学会賞受賞(産婦人科医で初受賞)。著書多数、近著に『若返りの医学 ―何歳からでもできる長寿法』ほか。最新刊はPHP新書『死ぬまで歩ける骨をつくる!本当は怖い「骨卒中」の防ぎ方』。