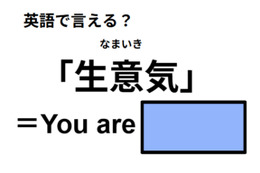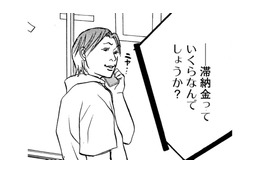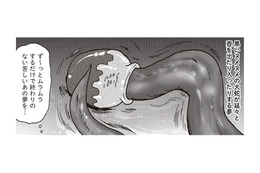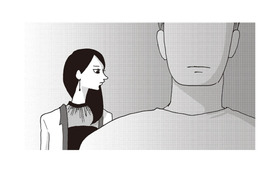*TOP画像/道廣(えなりかずき) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」36話(9月21日放送)より(C)NHK
「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「お墓」について見ていきましょう。
江戸時代以降、庶民の墓碑建立の始まり
日本において、庶民がお墓を持つようになったのは江戸時代以降といわれています。この時代、個人墓や夫婦墓が主流でした。現代においては角石形の墓石に家紋や名前が刻まれたお墓がもっとも一般的ですが、こうしたお墓は江戸時代の裕福な商人が始まりで、庶民が倣うようになりました。
『べらぼう』にはふく(小野花梨)と新之助(井之脇海)のお墓が出てきましたが、彼らのお墓には墓石などの目印はなく、土が盛り上がっていました。また、第31話では、新之助と蔦重(横浜流星)がふくのお墓の前に立ち尽くし、悲しみに暮れるシーンがありましたが、このシーンではふくのお墓と似た形態のお墓が数多く並んでいました。

蔦重(横浜流星) 新之助(井之脇海) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」31話(8月17日放送)より(C)NHK
庶民についても石塔を構えたお墓を建てるようになったのは江戸時代であるものの、経済的な理由などから遺体を指定された場所に埋め、その上に土饅頭を作るお墓を選ぶ人もいました。ふくと新之助はお金に余裕がなく、なおかつ彼らがこの世を旅立ったときの江戸は経済が低迷していたので、小さなお墓になったのだと思います。
地域社会の連携による葬儀の執行
葬儀を商いとする人たちが現れたのは江戸時代です。しかし、この時代の葬儀社は現代の葬儀社とは業務内容が大きく異なります。葬儀の執行に関わるほぼすべての業務を請け負っていたというよりも、葬具の制作や貸出を行ったり、葬儀を手伝う人の手配を行ったりしていました。
というのも、葬儀は村で協力して執り行っていたためです。「村八分」という言葉がありますが、十分のうち八分は関係性を絶たれる、もしくは無視されることを意味します。二分とは火災と葬儀のことで、これらのときだけは村八分になった人も村人と協力し合います。葬儀や墓穴堀りは隣人たちが相互扶助の精神で行っていたのです。
お寺と庶民が関係を持つようになったのも江戸時代でした。各村に僧侶が住むと、僧呂とお寺が結び付き、村人たちとお寺の間につながりが生まれます。幕府は寺檀関係を利用し、キリシタンの取り締まりを行ったり、民を管理したりしていました。それにともない、庶民の葬儀をお寺の住職が担うようになります。
江戸時代は死者をぞんざいに扱うことも
とはいえ、江戸時代中期に入っても、山や荒れ野には行き倒れになった人の遺体や骨が放置されていたともいわれています。また、幕府は心中を厳しく取り締まっていましたが、心中した男女は埋葬が許されず晒されたり、放置されたりすることも多々ありました。人びとは日常生活において遺体と遭遇することが少なからずあったのです。
吉原の遊女は亡くなると、“投げ込み寺”と呼ばれる寺に運ばれました。遊女は身につけているものを剥ぎ取られ、俵に詰められて葬られました。多くの遊女の遺体がいかにぞんざいに扱われていたのか分かるエピソードです。
現代では、重罪人の遺体であっても敬意を持って扱われますし、行方不明者の遺体の捜索が命がけで行われることもあります。江戸時代と現代では遺体に対する考え方も大きく違っていました。
本編では、江戸時代の庶民の墓や葬儀のあり方について解説しました。
▶▶ 腹を切り、豆腐に頭をぶつけて死を選んだ戯作者。命がけで笑いを生み続けた江戸の出版現場の悲劇耕書堂開業以来の最大危機とは【NHK大河『べらぼう』第36話】
では、戯作者たちに迫った黄表紙弾圧と、その中で命や人生を失った人々について見ていきます。
参考資料
米澤結『お墓、どうしますか? 変容する家族のあり方』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2018年
吉川美津子『図解入門業界研究最新葬儀業界の動向とカラクリがよーくわかる本』秀和システム、2010年