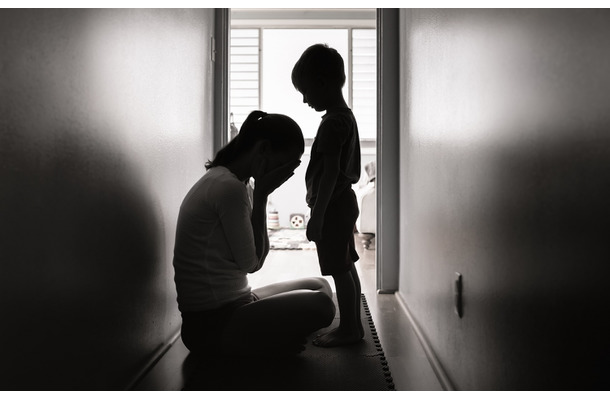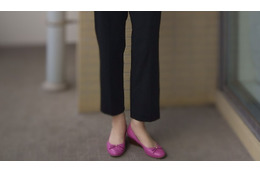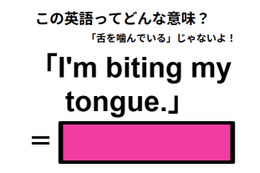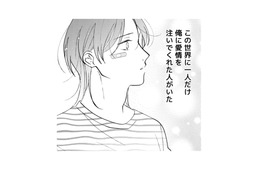この「家族のカタチ」は、「私たちの周りにある一番小さな社会=家族」を見つめ直すインタビューシリーズ。いまや多様な価値観で描かれつつある、それぞれの「家族像」を見つめることは、あなたの生き方や幸せのあり方の再発見にもつながるでしょう。
今回から2回にわたってお話をうかがうのは、健常児と重度知的障害児の兄弟を育てるシングルマザー・まどかさん(仮名・40代前半)です。20代で結婚後、30代で授かった第二子が重度の知的障害を伴う自閉症児と診断。それに追い打ちをかけるように待っていたのは、夫の裏切りでした。
かつての出来事を振り返るまどかさんの口からは「命を断つことも考えた」という衝撃的な一言も。ところが、今回のインタビューに答えるまどかさんの口調は、明るく、穏やかです。深き葛藤とどのように向き合い、乗り越えたのか――その道筋を探ります。
※記事中の画像はすべてイメージ画像です。
【家族のカタチ #10 障害とともに編】
『私が母親になっていいの?』心の傷がくすぶる初めての妊娠

shutterstock
「初めての妊娠がわかったのは結婚から3年ほど経った時。夫の喜びをよそに、私の胸には『母親になっていいのだろうか』『虐待をしてしまうのではないか』――そんな戸惑いと不安ばかりが募りました」。
14年前に出産した長男の妊娠判明当時の心境を、そう振り返るまどかさん。
自身は「至って普通の環境」で育ち、被虐待児でもなかった一方で、「あまりいい経験をしてこなかった」とも。いくつか質問を重ねると、親子間での心の傷つきが浮かび上がってきました。

shutterstock
たとえば、大学時代。ある日、学事課から告げられたのは「大学から除籍になる」という唐突な報せでした。親に支払ってもらっていたはずの大学の授業料が、知らぬ間に滞納されていたのです。慌てて事実を確認するうちにわかったのは、ギャンブル依存症に陥った母による、学費の使い込み。そればかりか、まどかさんが小さい頃から貯めていた貯金まで、きれいに消えていました。
大学へは急ぎの対応が奏功して、何とか卒業まで辿り着けたものの、この一件以来母が重ね続けた嘘は、まどかさんの心に大きな傷を残しました。
「今思うと、頭ごなしな物言いをしがちな親だったんですよね。私にとってはそれが普通の環境でしたが、信頼関係は醸成されにくかったのかもしれません。それに加えて、この除籍騒動。いまだに母を信じられないこの私が、果たして母として子どもを育てられるのか――そうやって不安を膨らませた気がします」。
孤独な育児を救ってくれたのは、義母だった

shutterstock
とはいえ、いざ生まれてみると、我が子に確かな愛情を抱くことができたまどかさん。かつての不安に捉われる暇もないほどに慌ただしい育児に奔走しつつ、すくすく育つ姿に大きな喜びを覚えました。ところが、妊娠を喜んでいたはずの夫は「育児に協力的」とは言い難い状況だったとか。
「最初こそ、夫は長男をかわいがっていましたが、間もなく、泣き声にも『うるさい』と言い放って、別室で過ごす時間が増えたんです。特に手を貸してもらえるわけでもなく、育児は完全に私の役目でしたね」。
実はまどかさんは、それ以前から夫との関係を対等だとは思えていませんでした。20代半ばで結婚を決断した頃は、夫のはっきりとした物言いに頼もしさを感じたものの、夫婦としての生活をスタートすると、精神的な逃げ場を奪われる要因となったようです。

shutterstock
「遠距離恋愛からの結婚を機に、私は知り合いが誰一人いない土地に引っ越しました。しかも夫は月の半分ほど出張。どうしても孤独に苛まれるんですよね。思わず涙を流すと『そんなのわかってて嫁いできたんじゃないの?』と怒られるんです。何か話しかければ『起承転結がない』と指摘されることもしばしば。子どもを授かる以前から、他愛もない雑談をしたり、共感し合ったりという日常は、あまりなかった気がします」。
当時を振り返る言葉の隙間に、寂しさと切なさをのぞかせるまどかさん。気持ちを共有しにくい夫婦関係で、一体どうやって日々の育児を乗り切っていたのでしょう?
「あの時私が頑張れたのは、義母の存在が大きいですね。実は当時、職場の事情で出産から4か月後に仕事復帰することになったんです。保育園も決まらず、どうしよう……と思っていたら、それを見た義母が、『私がお世話を引き受けるから、安心して働いておいで』と、環境を整えて背中を押してくれたんです。とてもいい方で、本当に恵まれていました」。

shutterstock
9時から17時まで仕事をこなし、帰宅と同時にワンオペ育児――それは目が回りそうな日々でした。それでも、あたたかな義母に支えられ、妊娠当初に抱いていた「私が母親になっていいのだろうか?」という思いは、いつの間にか静かに姿を消していました。それどころか、新生活に少し慣れた頃、まどかさんは「この子に、兄弟を作ってあげたい」と考え始めます。
「私にも夫にも兄弟がいましたから、お互いに兄弟がいる楽しさに触れて育った環境だったんですよね。だから、『2人目を作りたい』と、私から夫に相談しました」。
相変わらず、夫は育児に積極的に関わる状態ではありませんでした。。それでも、義母もあたたかく助けてくれるし、長男が楽しい環境で過ごすことの方が大事。
「何とかなるかな、何とかしよう、と思えたんですよね」。
『実母と自分は、全く別の人生を生きられる。そして、自分は一人ではない』――そんな気づきが、まどかさんの大きな変化を後押ししてくれたのかもしれません。
第2子出産、ところが――。

shutterstock
第一子出産から3年後。まどかさんは無事に、次男をその腕に抱きます。思い描いた青写真が現実となり、喜びに満ちた新生活となるはずでした。ところが、次男が一歳半検診を迎えた頃、4人家族となったまどかさん一家の日々に、静かに影が差し始めました。
「検診の場で『できないことが多い』と発達の遅れを指摘されたんです。たまたま同伴していた義母はとても心配していたのですが、私は『まったくもう、そんなこと言っちゃって!』と、あまり真に受けてはいませんでした。だって、目に見えて気になる様子も、育てにくさもありませんでしたから。個人差の範疇だと思っていたんです。
でも、数カ月が経ち、半年が経過しても、次男の口からは一向に言葉が出てこない。さすがに『あれ?』と思い始め、2歳ごろから療育機関に通い始めました」。

shutterstock
発達に関する診断が可能なのは、一般的に3歳ごろからと言われます。その診断を待たず、療育に通わせ始めたまどかさんでしたが、事態は思うように好転しませんでした。ようやく3歳を迎えた次男に専門医から告げられたのは、「知的障害を伴う自閉症」という診断だったのです。
「次男は現在小学5年生。ところ構わず『キキキキ』『トトトト』と声を発したり、パンパンと手を叩いたりします。こちらの言うことを理解できる部分もありますが、本人からの発語はありません。知能面での発達レベルは、今も2~3歳程度と言われています。次男の場合、この知的発達は年齢に比例して大きく成長するわけではありません。療育手帳の等級的には『重度』ですが、『最重度』との境目ギリギリのところですね」。
『命を絶つ』という選択の向こうに見つけた希望

shutterstock
幼い次男に突き付けられた厳しい現実。それと時期を同じくして、夫婦関係を大きく揺るがすもう一つの大きな出来事が、まどかさんに襲い掛かっていました。次男の出産前から長きにわたる、夫の裏切り行為が発覚したのです。
次男の障害がわかってからの夫は、『なんだか大変そうだね』とまるで他人事。『俺なりに心配しているんだよ』とは言うものの、具体的なサポートも寄り添いもない。それに裏切り行為が加わったのですから、まどかさんの気力が尽きるのも自然な流れでした。
「あの頃は、下の子を連れて命を断つことばかり考えていました。『この子は生きていても、将来大変なだけだ』って。夫が一緒に頑張ってくれるわけでもないし、未来が見えない。本当にギリギリの状態でした。でも、苦しみふさぎ込む日々を過ごしたある日、ふと思ったんですよね。『人生を終える』という究極の道を選べるなら、真逆の方向に振りきって『自分が生きたいように生きる』というもう一つの道も選べるんじゃないかって」。

shutterstock
それまで夫との関係に行き詰まり、幾度も「離婚」の選択肢が頭をよぎりつつも、自らの生活力のなさに足踏みしていたまどかさん。が、この考えに辿り着いたのを境に、2人の息子とともに、のびのびと自分らしく生きる方法を模索すべく、一気に舵を切ります。
まず着手したのは、離婚を認めてもらうための証拠集め。その傍らで、自身の働き方や暮らし方の徹底的なシミュレーションを開始します。障害児育児と両立させながらどれほど稼げるのか。障害児支援の充実度はどうか。生活面でのメリットが大きいのは、当時住まいがあった西日本なのか、それとも両親が暮らす都内なのか。――情報収集と検討を重ねた結果、辿り着いた答えは、「東京に住まいを移し、両親と一緒に暮らす」という道でした。

「都内は家賃も物価も高いけれど、各種手当や障害者への支援がとても充実しました。そして、両親の手も借りられるという安心感もある。
小学校入学を控えていた長男は、環境の変化に抵抗を示すのではと心配しましたが、離婚も引っ越しも、拍子抜けするほどすんなり理解してくれたんです。話をした翌日には、保育園で『僕、東京の学校に行くんだよ!』って友達にケロッと報告していたくらい。もちろん、心配させないように振る舞っていたのかもしれませんが……長男の前向きな姿にも背中を押してもらえました」。
こうして、時間はかかりつつも、離婚は成立し、新生活の方向が定まりました。それもこれも、絶望からふと視線をずらした先に見つけた新しい光を、まどかさんがしっかりと握りしめたからこそ。家族3人の新たな「家族のカタチ」が幕を明けたのです。
次回は、シングルマザーとして「自分の人生を生きる」日々で目にしている景色や、今後の自分と家族の生き方について思うことを伺います。
▶関連記事『「障害があってよかった」なんていえない。それでも11年間で、この子が私を変えてくれたこと【体験談】』
>>>こちらから読む