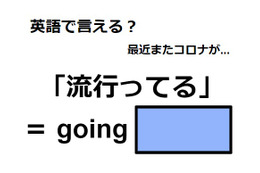こんにちは、ライターの岡本ハナです。
私の長女はADHDと強迫性障害を併せ持つ、いわゆる発達障害児ちゃん。
発達障害児の子育てにおいてよく言われるのが、「見通しが立たないと不安になるから、先回りしてサポートを」ということ。でも最近、それが彼女の“自主性”を奪ってしまっているのでは?と感じるようになってきました。
「ペアトレ」で学んだ“褒め育て”がもたらしたこと
ADHDと強迫性障害の診断後、すぐに受講したのが「ペアレント・トレーニング」(通称:ペアトレ)。子どもの褒め方や注目すべき行動、親としての接し方を学びました。
当時の私はとにかく必死で、とにかく小さなことでも褒めまくったので、本人には「なんかうざい……」と思われてしまったようですが(苦笑)、弟と妹たちもまとめて褒めまくっているうちにだんだんと良い影響も感じられたので、コツコツと続けてきました。
静かな反抗期と“褒められ慣れ”の副作用?
中学生になった長女は、ただいま絶賛反抗期です。でもそれは普通の反抗期ではなくて「静かな」反抗期。ものすごく落ち着いたテンションで、「食欲ないけど、ご飯食べてあげてるんじゃん。私、えらくない?」なんて言ってきます。
……え、なにそのセルフ賛美。褒められ慣れすぎて、そんなこと言っちゃってる!?
ほかにも「ママ、水(=飲みたい)」なんて、まぁ昭和の父ちゃんみたいなセリフも平気で投げてくる。しかも、「隣の部屋から話かけてくる→私、返事できない(気がつかない)→ブチギレ」の流れが定番化。
「なんでママは私の話を聞いてくれないの?!」と自分中心の発言にびっくりしました。(そもそも「聞こえないような話しかた」をしなければいいのでは…)
これは私があまりに手厚くサポートしすぎた結果なのかも、と、ちょっと反省モードに。
自立を促すつもりが、甘えを強めてたかもしれない
ペアトレで学んだことは否定はしません。当時の長女は「不安を減らすための先回り」はたしかに必要だった。褒められた経験は、彼女の安心材料や土台になってくれたと思っています。
けれどそれが、彼女自身の“考える力”や“対処する力”を育てる機会を減らしてしまっていたとしたら……? 「褒め育て」と「過保護」は、ほんとに紙一重なんだなぁと痛感しています。
本編では、発達障害をもつ娘を褒めて育ててきた私が、「静かな反抗期」を通じて、過保護と褒め育ての微妙な境界線に気づいた経験をお届けしました。
▶▶ 「いつまでも親はいない」発達障害の娘に今こそ伝えたい、“自分でどうにかする力”の育て方
では、自立と支援のバランスに悩むなかで私が改めて気づいた「娘自身が困難を乗り越えるための力」についてお話しします。