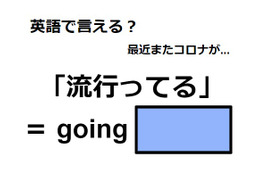*TOP画像/菊園(望海風斗) 京伝(古川雄大) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」40話(10月19日放送)より(C)NHK
「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「梅毒」について見ていきましょう。
梅毒は江戸時代に効果的な治療法がなく、死に至る危険性もある病気だったが……
本作の第38話「地本問屋仲間事之始」では歌麿(染谷将太)の妻・きよ(藤間爽子)が梅毒を患いこの世を去りました。
梅毒はヨーロッパで1400年代後半に大流行し、1520年には日本に到達しました。性的な接触をした際に梅毒トレポネーマが傷口や粘膜から侵入し、感染します。
きよは歌麿と出会う前は洗濯女として生計を立てていましたが、生きていくには不特定多数の男に女を売らざる負えない境遇にあったため、梅毒に感染したと考えられます。
過去の放送回において、きよの足の赤い斑点が歌麿ときよのそう遠くない未来を暗示するかのように映し出されたシーンがありましたが、肌の赤いブツブツは梅毒の一般的な症状の1つでした。
また、晩年のきよは錯乱状態に陥り、薬を持って訪ねてきた蔦重(横浜流星)にもひどくあたっていました。つよ(高岡早紀)はきよのこうした症状を梅毒の症状の1つと蔦重らに説明していましたが、中枢神経系梅毒の場合、脳が侵され、誇大妄想や言葉のもつれ、知能低下などの症状を引き起こすこともあります(*1)。

歌麿(染谷将太) きよ(藤間爽子) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」38話(10月5日放送)より(C)NHK
梅毒は身体を少しずつ蝕み、中長期的にわたって苦しみに耐えることを強いられる病です。現代においては治療薬があるため早い段階で完治できることがほとんどですが、当時は梅毒を患った状態で生き続けなければなりませんでした。
江戸時代、遊女が梅毒にかかると、稼ぎが悪い遊女は放置されることがほとんどでしたが、効果の真偽はともかくとして、治療法がまったくなかったわけではありません。当時、梅毒に効果があると考えられていたのは水銀でした。現在は水銀が梅毒の治療に効果がないことは明らかになっていますが、梅毒は感染初期にしこりや発疹が出た後に症状が出て、消失するため、症状が一時的に落ち着くのは水銀の効果と勘違いされることが多々あったのです。
註
*1 大前利通(監修)『症状からすぐにひける家庭の医学事典: 実用版』参照
梅毒に感染してこそ“一人前”の遊女
梅毒は杉田玄白をも治療法に悩ませた、死の危機に瀕する恐ろしい病でした。
しかし、幕府は梅毒の感染源が遊郭であることに薄々気付いていたものの、取り締まりを行うことは長らくありませんでした。ちなみに、鎖国が解かれた後、外国人が入ってくるようになると、イギリス人の提案によって遊郭に検査所が設けられ、性病検査が実施されるようになります。
遊郭で働く女性たちは梅毒を内心恐れていたとしても、少なくとも建前上はさほど気にしていなかったようです。それどころか、遊女が梅毒にかかることは「鳥屋(とや)につく」といわれ、梅毒に感染し寝込む時期が過ぎ、一時的に回復すると、“一人前”とみなされたのです。
また、梅毒に感染すると子どもが生まれにくくなるため、遊郭側にとって遊女の管理を行いやすいという利点もありました。
さらに、遊女は梅毒の症状が悪化しても働き続けなければなりませんでした。ただし、容姿が重視される吉原の遊郭や一流の遊郭では働けなくなるため、客と安い金額で取引を行っている岡場所の女郎、道に立って客をとる夜鷹(=立ちんぼ)として生計を立てなければならなくなります。
不特定多数の女性たちと大人の遊びを楽しんでいた男性たちは梅毒の恐ろしさを知りつつも、どこか軽く見ていました。男性の中には梅毒感染は遊び慣れていることを証する“ステイタス”と考える者もいました。
彼らは遊女が梅毒に感染しているリスクを承知の上で遊んでいただけでなく、夜鷹の梅毒の感染率が一流の遊郭で働く遊女よりも高いことについても察していました。それでも、自身の欲に負け、価格の安さに惹かれ、梅毒に感染することを承知の上で遊んでいたのです。
本編では、梅毒に侵されながらも男を抱き続けるしかなかった遊女たちと、その悲劇を“遊び慣れた証”と軽んじていたいた男たちの現実をお伝えしました。
▶▶「尽きることのない、人の欲」きよを失った歌麿が描く、痛みの先にある“生”のエネルギー
では、絶望の淵にいた歌麿が再び筆を取り、蔦重とともに“欲”という人間の力を見つめ直す姿をお届けします。
参考資料
大前利通(監修)『症状からすぐにひける家庭の医学事典: 実用版』西東社 2010年
歴史の謎を探る会 『江戸の性生活夜から朝まで Hな春画を買い求めた、おかみさんたちの意外な目的とは?』河出書房新社 2008年
本郷和人、 井沢元彦 『疫病の日本史』 宝島社 2020年