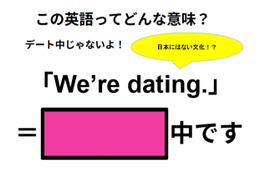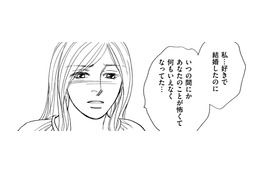鹿児島大学の大石充教授と ミツカン中央研究所の共同研究により、週1回以上お酢を使った料理を食べている人は、毎日排便がある傾向にあることが初めて明らかになりました。
前編記事『どの家にもある「液体」の料理を週に1回以上食べているとお通じが◎?鹿児島大学×ミツカンの共同研究が話題!』に続く後編です。
すでに報告されている「お酢の健康効果」もこんなにあったけれど、今回新たにもう1つ!
お酢は、糖質を含む食材をアルコール発酵させた後、酢酸発酵させた酸味のある液体調味料を指します。毎日継続的にお酢をとることで、これらの効果があると論文で報告されています。
・食後の血糖値上昇を抑える
・肥満気味の人の内臓脂肪減少をサポート
・高めの血圧を下げる作用
・運動後の疲労感を軽減
そこに今回、「便通改善への可能性」も新たに加わったのです!
大石教授が語る「お酢と便通」の新たな可能性
本研究を主導した鹿児島大学の大石充教授は、次のように語ります。
「高齢化率43%の多職種による高齢者コホート研究『垂水研究』の解析により、お酢を使った料理を食べる習慣のある方々の便通がよいことが示されました。
今回のお酢を使った料理の摂取頻度と排泄状態との関連を報告した研究は、本研究が初めて。お酢の新しい健康効果として非常に意義深いです。さらに科学的な関係性について、研究をかさねていきます。
便秘にお悩みの方も多いと思いますので、ぜひお酢を食事に取り入れてみてください」

1990年大阪大学医学部卒業後、2007 年同大医学系研究科講師、2013 年から鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・高血圧内科学分野教授を務める。医師 への高血圧治療の指導を行う循環器内科のスぺシャリストであり、地域医療の底上げに尽力。2017 年からは垂水スーパーバイザーに就任し、多職種によるチーム医療コホート研究を推進。さらに、産学行連携の共同研究体制を強化し、長期的な情報発信を目指している。
ではどう取り入れていく?「意外ですが、納豆にもよく合うんですよ」
これまでお酢をとる習慣がなかった方も、毎日のスッキリ排便を目指して、今日からぜひ食事に「お酢」を取り入れてみてはいかがでしょうか?腸がすっきりキレイになると、健康はもちろん、生活全体の質(QOL)もアップするかもしれません。
ただし、お酢をそのまま飲む場合は、1日の摂取目安は大さじ1~2杯程度にしましょう。飲んだ後は、口内に酸が残るのを防ぐため水を飲みましょう。
さっぱり納豆ご飯

▶︎材料(2人分)
ご飯/茶碗2杯
納豆/2パック
穀物酢/小さじ2
きざみのり/適量
▶︎作り方
器にご飯を盛り、添付のたれと「穀物酢」を混ぜ合わせた納豆をかける。きざみのりを散らして。
りんごのリフレッシュドリンク

▶︎材料(1人分)
りんごジュース/1カップ
りんご酢/大さじ1
▶︎作り方
グラスにりんごジュースを入れ、「りんご酢」を加えて混ぜる。
わかめときゅうりの酢のもの

▶︎材料 (2人分)
きゅうり/1本
わかめ(もどしたもの)/20g
塩/ひとつまみ
<合わせ酢>
穀物酢/大さじ1と1/2
砂糖/大さじ1
しょうゆ/大さじ1/2
水/大さじ1
▶︎作り方
きゅうりは薄い輪切りにする。塩をまぶし、しんなりしたら水けを絞る。
わかめは食べやすい大きさに切る。<合わせ酢>はよく混ぜ合わせる。
ボウルに[1]のきゅうりとわかめを入れ、<合わせ酢>を加え、よくあえて味をなじませる。
鶏のさっぱり煮

▶︎材料2人分
鶏手羽元/8本(480g)
ゆで卵/2個
ブロッコリー/適量
<調味料>
穀物酢/100ml
しょうゆ/大さじ3
砂糖/大さじ3
▶︎作り方
手羽元はよく水けをふく。
鍋に[1]と<調味料>を入れ、強めの中火にかける。
煮立ったらふたをして、中火で15分ほど、煮汁が1/2~1/3程度になるまで煮る。
ゆで卵を加えて煮汁をからめ、手羽元と一緒に器に盛り、ゆでたブロッコリーを添える。
※しょうが、にんにくを手羽元と一緒に入れると風味が増します。チューブの場合は各小さじ1。
“便が出ない”というストレスは、日常生活に大きな影響を及ぼします。これから少しずつでも取り入れてみてはいかがでしょうか。毎日、スッキリを目指しましょう!