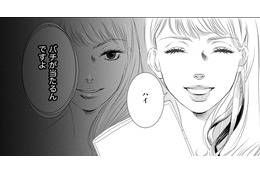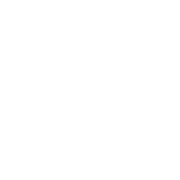この「家族のカタチ」は、「私たちの周りにある一番小さな社会=家族」を見つめ直すインタビューシリーズ。いまや多様な価値観で描かれつつある、それぞれの「家族像」を見つめることは、あなたの生き方や幸せのあり方の再発見にもつながるでしょう。
今回から2回にわたってお話をうかがうのは、ホームページ制作会社で正社員として働く、yura(ゆら)さん(仮名・40代前半)。
2020年から、世間に大きな影響を与えたコロナ禍。そのど真ん中で、yuraさん家族を襲ったもう一つの大きな不安――それは、実母の認知症でした。最初の診断から間もなく5年。母の病状が進行した今は、介護に加え、自身の仕事、さらにはこの夏6歳になる娘の子育てと、いわゆる「ダブルケアラー(※)」として慌ただしく奔走しています。
心の整理も追いつかないほどに進行が早い母の認知症と向き合いながら、それでも前を向き続けるyuraさんの「家族のカタチ」についておうかがいしました。
なお、本記事中では、カメラが趣味だったというyuraさんのお母様が撮影したお写真を併せてご紹介させていただきます。
(※)ダブルケアラー:「親の介護」と「子育て」という2つのケアを同時に行なう状態にある人。日本国内では、推計約25万人以上にのぼるともいわれている(2016年内閣府男女共同参画局による調査)。
【家族のカタチ #9 母の違和感編】
発症率1%。「まさか、あの多趣味でしっかりした母親が……」大ファンだった俳優の存在が、母から消えた。

2020年8月にyuraさんの母親が撮影した蓮の花。家族が異変に気づいたのは、この頃だった。
「前頭側頭型認知症」――それが、当時67歳だったyuraさんの母親が患った認知症でした。一説によると、認知症全体に占める割合はわずか1%と言われることも。国では難病指定もされており、現在、根治的な治療法は確立されていません。
「母は、とてもしっかりした人でした。スマホを使いこなすのはもちろん、自作のパソコンで在宅ワークもしていたし、なんといっても多趣味。特にカメラはセミプロ級の腕前で、写真コンテストに入賞したこともあったんですよ。大きなレンズや機材を担いで毎日のように撮影に出かけていましたね。人柄も穏やかで、たまに父の愚痴をこぼしても、気持ちをすぐに切り替えてあっという間に元通り。『自慢の母』です」。
そんな母親に異変があったのは、2020年の夏。当時両親と同居していたyuraさんの弟から、突然一本の電話がかかってきました。
「母は、俳優の織田裕二さんが大好き。ところが、ドラマに登場した姿を見て『この人、誰?』と言っている。『ちょっとおかんがおかしいわ』と弟が言うんです。年を重ねれば物忘れは増えますが、誰かが助け舟を出せば『ああ、そうだった!』と反応しますよね。でも、母は違った。名前を伝えてもキョトンとして……あれだけ大好きだった人の存在自体が、ぽっかり消えていたんです」。

「あまりにしっかりした母親だったから、まずは外傷性の認知症を疑っていました」とyuraさん(2020年7月 母撮影)
その瞬間、「認知症」の可能性が頭をよぎりつつ、「あんなにしっかりして、アクティブな人が、まさか……」と、大きなショックに襲われたyuraさん。
「『どうしよう、どうしよう』と、さすがに戸惑いました。明らかにおかしいけれど、現実を見たくない。――でもね、すぐ動き始めたんです。というのも、認知症についてあれこれ調べてみたら、投薬で進行を遅らせることが可能なケースもあったから。場合によっては『外傷性(脳梗塞や脳出血などによって認知症症状が引き起こされるケース)』かもしれないと思いましたし、それならなおさら1日でも早く治療を始めた方がいい。ショックに打ちひしがれるよりも、今できることを、って思ったんです」。
「今すぐ受診して」ほしい娘、「ただの物忘れだ」と受け入れない父

家族それぞれの気持ちは揺れ、対応が前進せずもどかしい気持ちを抱える日々が続いたという(2020年8月 母撮影)
とはいえ、認知症や介護に何の知識もない身に降りかかった晴天の霹靂。yuraさんが懸命に自力でウェブ検索しても、田舎にある実家の周りにはなかなか専門医が見つかりません。
「手探りで右往左往するうちに、どうやら医療や福祉などの相談に乗ってくれる『地域包括支援センター』なるものがあるらしい……と、ようやく相談相手に辿りついたんです。職員の方が近場の『ものわすれ外来』を案内してくれたので、すぐに弟に『ここに行って』とLINEを送りました」。
ところが――。
「父が、抵抗するんです。『行かんでもいい、ただの物忘れやから』って。万が一の可能性を認めたくなかったんでしょうね。一方で頼みの綱の弟は、『仕事があるから』と、すぐには動いてもらえない日々が続きました」。

「小さな子連れで帰省するには、自身のコンディション的にも社会情勢的にもハードルが高い時期だった」とyuraさんは振り返る(2020年11月 母撮影)
2020年といえば、コロナ禍に陥った直後で、世間は混乱真っ只中。長距離移動や人との接触を避けるように呼びかけられている時期でした。しかも当時のyuraさんは、ちょうど1歳になったばかりの娘を抱える身。
「事情が事情なので、『実家に帰ろうか』と言っても、乳幼児と高齢者で接触のリスクも大きいから『帰ってこんでええ』と言われてしまう。夫は週末も仕事ですから、帰省を強行するにしても、実家まで片道2時間の道のりをワンオペで移動するしかない。しかも育児疲れで抑うつ的な時期でもありました」。
母親を心配する気持ちの前に横たわる多くのハードルが重なった結果、「私は遠くから『いつ病院に行くの?』って発破をかけるしかありませんでした」。そんなもどかしさを抱えながら、粘り強く働きかけ続けて半年が経った頃、ようやく受診の機会が訪れたのだそう。

夫婦で散歩の帰り道に、夕焼けが写り込むシャボン玉を撮影した2021年2月。母は『認知症』と診断された。
「現実を受け入れない父に業を煮やした弟が、父に条件を出したんです。『台所からスプーンとフォークを持ってきて。この名前がわからなかったら、病院に連れていきや』って。すると、母はどちらも答えられなかった――」。
『じゃあ、連れてくわ』と、重い腰を上げた父親に連れられた母に病院で下された診断は、家族の予想通り『認知症』。2021年2月のことでした。
里帰り出産の拒否、途切れる会話……今思えば、あれは予兆だった。

風景に美しさを見出し切り取る感性の一方で、「この頃は既に、母は一人で少しずつ何かがおかしい自分に気づいていたのかもしれない」とyuraさん(2019年3月 母撮影)
「これは後出しじゃんけんに過ぎないのですが……今にしてみれば、いろんな予兆があったんですよね」と、yuraさんは診断に至る以前の出来事を振り返ります。
「2019年の前半――つまり俳優さんを忘れて認知症を疑ったあの日から遡ること1年半くらい前でしょうか。私の里帰り出産について母に相談したんです。すると、母はしばし考えて、『自信がないからやめて』って断ってきたんですよね。しっかり者の母でしたから、少し意外だったのを覚えています。
尋常ではないレベルで言葉が出てこない様子も、そういえば同じ時期に感じていました。母とはしょっちゅう電話をしていたのですが、会話が、急にぷつんと途切れるようになったんです。体感で1分ぐらいかな……『あれ?電波が途切れた?』と思って、『もしもーし』と何度か呼びかけると、また会話が再開される、という具合に」。

「出産直後やお宮参りに孫に会いに来た母は、私たちにいつも通りに接してくれた」とyuraさんは振り返る(2019年9月 母撮影)
さらに、2019年8月の出産後にはこんな出来事も――。
「実家とは頻繁にビデオ通話をして、孫の顔を見せていたのですが……母が、画面に出てくれなくなっちゃったんですよ。『私はいいから……』と部屋の奥に逃げちゃうんです。
あの時の母は、同居家族の存在はまだ認識できました。けれど、多分、画面の先にいる私が誰なのか、『ビデオ通話』が何をしているかがわからなくて、怖かったんだと思うんです」。
「どれも、今だから答え合わせができること」と心の半分では割り切りつつ、残りの半分では「もっと踏み込めたのではないか」と、yuraさんは家族ならではの葛藤をにじませます。
「恐らく、私たちが気づくよりもずっと前から、母にしかわからない違和感があったんだと思います。そして不安も一人で抱えていたのかな。でも、日頃から感情を波立てたりしない人だったから……私たちに何も言わなかった」。
「だったら、診断が下った今からでも、その戸惑いや不安に、耳を傾けたい」――そう考えたyuraさん。ところが、その願いは叶いませんでした。
何度も唱えて練習した娘家族の名前――。母が最後に呼びかけてくれたあの日

5月の晴れた日、念願の母との再会。穏やかなひと時がようやく訪れた(2022年5月 母撮影)
コロナ禍が明け始めた2022年5月。診断後の母親とyuraさんが、初めて対面できる機会が訪れます。診断からは1年3ヶ月が経過し、yuraさんの娘は2歳9ヶ月を迎えていました。
「ようやく子連れで実家に帰れました。会った時に、娘だと認識してもらえるのかな……って、私は不安でいっぱい。ところが、いざ再会したら、ずっと私の名前を呼んでくれたんです。それが、ものすごく嬉しかった」。
うららかな日差しが気持ちの良い初夏、みんなでピクニックをしながら語らうひと時も。yuraさん家族にとって幸せなひと時だったに違いありません。

「母に名前を呼ばれたのは、あれが最後だった」(2022年5月 母撮影)
「一方で、やはり母の症状は進行していたんですよね。ピクニック中にトイレに行きたいと言い出し、『一人で大丈夫だから』と席を外したまま、20分経っても帰ってこなくて……。みんなで探し回ってようやく、迷い途方に暮れる母を見つけました。
――さっき、『私の名前を呼びかけてくれて嬉しかった』ってお話しましたよね。これは後から弟に聞いた話なのですが、私たちが到着する前に、母は手元のメモ用紙に私と娘と夫の名前を書き留めて、何度も繰り返し唱えて練習していたそうなんです。名前を忘れないように、呼びかけられるように……母の思いと努力が嬉しくて、でも母の心の内を思うと切なかった――」。
ずっと前から、「母の不安な気持ちを聞きたい」と願っていたyuraさん。この帰省では、やっと寄り添えると考えていました。
「たくさん話したかったし、母の話も聞きたかった。けれど、『もう話しかけないで』という空気が、なんとなく漂っているんです。表情にも緊張がにじみ、なんだかしんどそうな感じで……私たちの名前を呼ぶ、それが母の精一杯だったんです。もっと話しかければよかったという後悔は、正直残っています。でも、母の負担を思うと、そうはできなかった。――母に名前を呼んでもらえたのは、あれが最後だったと思います。それから間もなく、私たちの名前は忘れてしまいました」。
症状の進行を食い止められない、非情な現実。その様子を遠方から見守るしかなかったyuraさんでしたが、直後に訪れるアフターコロナの到来とともに、ダブルケアラーとして、介護の中心人物として奔走する日々が始まります。
関連記事『「入れる施設はありません」介護のプロもお手上げ。認知症の母、仕事に子育て……それでも私が、心折れずに向き合えた理由とは?』では、時々刻々と変化する症状の進行、そして次々と降りかかる無理難題に自らの心を整えながら挑む、yuraさんの「家族のカタチ」をお届けします。
▶▶つづきを読む >>>関連記事はこちらから