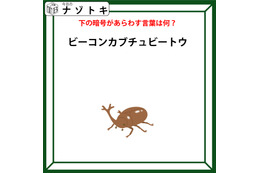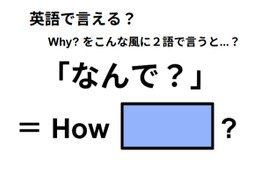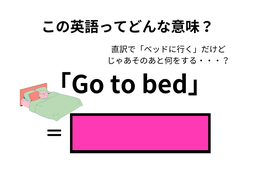静岡県三島市在住のライター神田未和です。看護師・助産師としてキャリアをスタートし、グローバルヘルスの世界で働いてきました。夫の闘病生活を機にライターに転身し、女性のライフステージに応じた健康情報発信をライフワークとし、執筆活動をしています。
この連載では、思春期のお子さんをもつ親御さんのリアルな悩みや戸惑い、その対応策の体験談を紹介しています。誰かの体験談をきくことで、新しい視点に触れ、「わが家の思春期」への対応の糸口が見つかるかもしれません。親御さんだけでなく、同じ時代を生きる女性たちの声や思春期世代のリアルを知ることで、新たな気づきが得られるかもしれません。
インタビューを受けてくださったのは、東京都23区の中でも教育への関心が高い家庭が多いエリアに住む、看護師のAさん(43歳)。夫婦共働きで、12歳の息子さん(今年から中学1年生)の育児に奮闘中です。特性のあるお子さんの個性を大切にしながら、思春期特有の課題にどのように向き合ってきたのか、貴重な体験談をお届けします。
【シリーズ「思春期こども」 反抗期と中学受験 編】
「触んな」「近づくな」「キモい」…小学校5年生の終わりから始まった息子の暴言への向き合い方

shutterstock
―――小学校高学年から思春期に起こる心や体の変化がはじまる子もいますが、息子さんはどうでしたか?悩んだり、戸惑ったりしたことはありますか?
息子は5年生の冬頃から急に背が伸び、今は私を超して160cmあります。声変わりやひげも生え、たぶん下の毛も生えてきたと思います。なぜそう思うかというと、それまではお風呂上がりに見えても気にしていませんでしたが、隠すようになったので。さに、この頃から私や夫に対する息子の暴言が増えて、戸惑いました。
―――どんな暴言だったのですか?
色々ありすぎて覚えてないですが人格否定のような感じでした。たとえば、「うっせー」「触んな」「近づくな」「キモい」とか……。最初に聞いたときは「えっ、キモいとかいうんだ⁈」と驚きました。正式な診断は出ていませんが、息子はADHDの傾向があり、療育に通っていました。小学校では1年生から4年生まで情緒学級に通い、4年生の時に大丈夫と判断されて卒級しています。小学校低学年頃の息子は、先の見通しが立たない状況に置かれると、私に感情をぶつけるのですが、理由がわかるので対処できていました。それに対して、5年生の終わりに始まった暴言は、理由がわからず戸惑いました。低学年の頃は、友達への攻撃的な言動もあり、対応に苦労しました。でも、5年生からの暴言は家族に限られていて外ではトラブルがなくなったので、少し気持ちは楽でした。
―――息子さんの暴言にどのように対応していたのですか?
落ち着いたとはいえ、現在進行中です。息子が暴言発動モードに入ったときは、「他人」と思うことにしています。「この暴言はホルモンのせい、私のせいじゃない」と自分に言い聞かせて、息子へ余計なことは言いません。「早く寝なさい」とだけ伝えて、私は1人こっそりワインを飲む…が、暴言モードに入ったときの対応策。はやく寝て体調を整える方がいいですしね。
とはいえ、あるときは私が息子に「ふざけんな、何様なんだ!」怒鳴ってしまったこともあります。私も息子も柔道をしていたので、取っ組み合いのケンカもしました。私は「どんな状況でも手を出したら、その時点で負けだよ。」と息子に伝えてきたのに、自分が手を出してしまい……。最近になって、息子から「あんなに絶対手を出すなと言ってたのに、お母さんは僕に手を出したよね。」と言われます。そのたびに「はい。その通りです。ごめんなさい。」と謝ります。こうした会話ができるようになった息子の成長をうれしく思う反面、私が手を出してしまった事実は消えません。他の方法はなかったのかと毎回反省、そして葛藤です。
戸惑う心を救ったのは、大好きなサッカーとその仲間。チームメイトは子育ての大先輩

shutterstock
―――お子さんの対応に苦労していたとき、どのように気持ちを保っていたのでしょうか?
私にとって大きかったのは、サッカー仲間の存在です。高校時代にサッカーをしていて、子どもが生まれた後「ママさんサッカー」の存在を知り、再開しました。所属チームには、成人したお子さんをもつママさんなど、子育て経験豊富な先輩が多く、経験談を聞くことができます。練習や試合の合間に悩みを打ち明けると、先輩たちが、「わかる!」と励ましてくれたり、「うちの次男は反抗期がひどくて壁に穴を開けたよ」と教えてくれたり、救われました。
ママ友など、子どもが生活している地域で親同士が話すときには、話した内容がどこで誰に伝わるかわからないので、つい慎重になります。それに対し、サッカー仲間は「サッカーが好きな人」のつながりで、広いエリアから集まり、世代もさまざま。みんな仕事と子育てで忙しい中、サッカーがしたくてどうにか時間を作って来ているので、メリハリがあり、居心地がいいんです。息子の特性のことを話していると、「実はうちも…」と、同じ悩みをもつ母親同士でさらりと会話することができます。
サッカーは、人間性がすごく表れる競技なので、プレーを通じてお互いの性格や考え方が見えてきます。「Aさんはこういうところがある。それはダメだよ」と率直に言われることもあるし、「あのプレー良かったよ!」と褒められることもあります。それが子育ての話にもつながり、「子どもにそこまで伴走できるのすごいよ」と褒めてもらえたり、ダメ出しも含めフィードバックをもらえたりします。
◆自分の好きなことを通じた社会的なつながり
ママさんサッカーは「好きなこと」と「人」と「運動」とのつながりが、人を元気にしてくれる場所なのですね。Aさんが所属するチームは、地域のサッカースポーツ少年団に通う子どもたちのお母さんたちが、「私たちも蹴ってみよう」と集まり始まったそうです。こうしたママさんサッカーチームは、全国各地に広がっています。ママの枠を超えて、30歳以上の女性なら誰でも参加できるチームもあるようです。子どもの学校以外のママコミュニティを探しおくというのはいいかもしれませんね。
中学受験、競争社会のストレスで、漢方外来に通う小学生は珍しくない

shutterstock
―――ところで、お子さんとの会話の中で「みんな~~~している」といった、同世代の子どもたちの様子が伝わる最近の話題はありますか?
私が住んでるエリアでは中学受験の話題が多いです。私は息子と同じ小学校の卒業生ですが、自分が5年生のときと今を比べると全く状況が違います。あるお母さんは、子どもが小学3年生のときに、「みんな受験すると言ってるんだけど…」と伝えられ、わが子の受験を考え始めていました。息子も受験しましたが、受験期はすごくきつかったです。
―――どんなところがきつかったのでしょうか?
一番は塾にかかる費用です。6年生のときだけで約200万円かかりました。私が働いてる目的は塾代を稼ぐこと(笑)。
もともとは公立中学校に進学してほしいと考えていました。でも、周囲から「特性のある子はあの環境ではつぶれてしまう」と聞いて、不安を感じていました。最終的に息子から「給食が食べられないから受験したい」と希望があり、決めました。息子は給食の舌触りが苦手なようで、2年生のときに頑張って1口食べたら吐いてしまい、それを友達に指摘され、いじめの始まりみたいになり…。大人が介入して大事には至らなかったものの、息子のトラウマになっています。それからは、学校から許可を得て、毎日おにぎりだけ持参していました。
―――中学受験を選択する理由には、家庭ごとにさまざまな背景があるのですね。
「中学受験がすべて」のような風潮がある社会では、子どもたちに大きなプレッシャーがかかります。息子は幸い合格でき、それが彼の自信にもつながりました。一方で、燃え尽きる子や、学校で荒れる子もいます。小学校4年生でも、「おまえ、あそこの塾の〇〇クラスなんだろう」といった成績による差別が子ども同士の間で起こることもあるようです。
息子は、朝起きられないことが多くて、漢方外来を受診して、処方された漢方薬を飲んだら、体調が良くなりました。 漢方外来の医師は 「中学受験で体調不良になったお子さんをたくさん診ている」と話していました。知人の娘さんも、漢方外来に通っています。本当にいろいろあります…。
▶▶関連記事を読む
『「もしパンツが白く汚れたときは…」性教育より情報社会を生きるための教育が優先されているからこそ、教えておきたいこと』