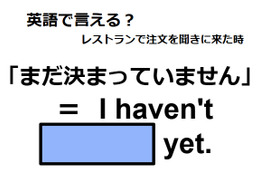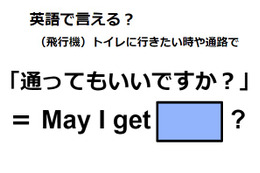元国税職員さんきゅう倉田です。好きな減価償却資産は「建物付属設備」です。
35歳から受験勉強を始めて、3年間勉強し、38歳で東京大学に入学しました。
4月から経済学部の3年生だ。
入学するまで知らなかったけれど、東大はすべての学生が教養学部に2年間所属する。
▶東大受験より難しい!?教養学部の期末試験
1週間で10科目!受験より難しいかもしれない期末試験
2年秋の「進学振り分け」で進学する学部の希望を提出し、成績によって選抜され、進学先が決定する。2年のAセメスター(秋学期)は、その進学先の授業を先んじて受け(持ち出し科目という)、学部によっては駒場と本郷を行ったり来たりする。
教養学部の期末試験は1月の下旬に行われるが、後期課程の持ち出し科目の場合は、2月上旬に実施され、ぼくは1週間で10科目の試験と向き合った。
ミクロ経済学と、マクロ系経済学と、統計と、ファイナンス、経済史、経営、会計だ。
各科目は、分厚い参考書1冊分程度を10月から1月の3カ月半で修める必要があり、難度も高い。
おそらく東大受験より難しい。
▶東大には推薦入試がある
範囲が限定されている分、短い期間で習得しやすいが、参考書を読んでも理解できない学生、覚えられない学生はいるだろう。
実際の試験は参考書と比べると難しくなかったが(ミクロ経済学の定期試験の過去問には「“代替“の読み方を答えなさい」という問題があった。)、試験勉強中の肉体的・精神的負荷は小さくなかった。目の下に大きなくまを作っていた友人もいた。
普段は駒場キャンパスで授業を受けている経済学部内定生も、定期試験は本郷キャンパスで受けるため、はるばる通っている。本郷キャンパスに来ると、“東大生”という感じがする。
試験が終わって、一息つくと東大の推薦入試の合格発表だ。
東大にも推薦入試が存在する。合格に大事な素養とは
国立大学の受験は、前期と後期に分かれている。
ほとんどの学生が前期日程で合格し、そこで合格しなかった受験生は後期日程で受験することがある。
▶つづきの【後編】では、東大の推薦入試で合格する人の特徴とは?についてお伝えします__▶▶▶▶▶